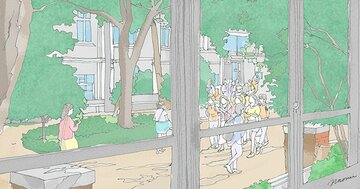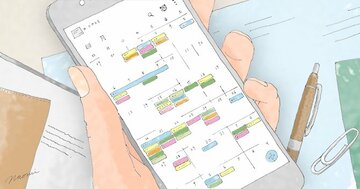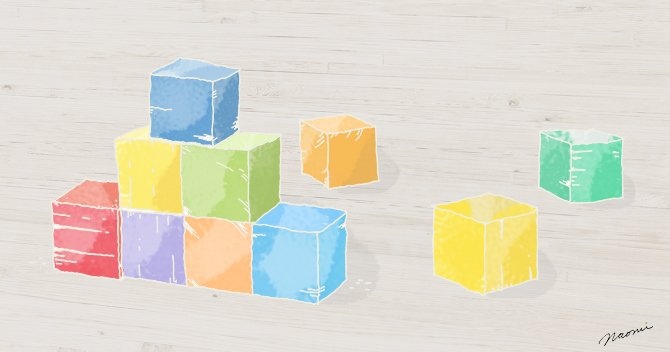
学生をはじめとした若者たち(Z世代)はダイバーシティ&インクルージョンの意識が強くなっていると言われている。一方、先行き不透明な社会への不安感を持つ学生も多い。企業・団体はダイバーシティ&インクルージョンを理解したうえで、そうした若年層をどのように受け入れていくべきなのだろう。神戸大学で教鞭を執る津田英二教授が、学生たちのリアルな声を拾い上げ、社会の在り方を考える“キャンパス・インクルージョン”――その連載第14回をお届けする。(ダイヤモンド社 人材開発編集部)
* 連載第1回 「生きづらさを抱える“やさしい若者”に、企業はどう向き合えばよいか」
* 連載第2回 ある社会人学生の“自由な学び”から、私が気づいたいくつかのこと
* 連載第3回 アントレプレナーの誇りと不安――なぜ、彼女はフリーランスになったのか
* 連載第4回 学校や企業内の「橋渡し」役が、これからのダイバーシティ社会を推進する
* 連載第5回 いまとこれから、大学と企業ができる“インクルージョン”は何か?
* 連載第6回 コロナ禍での韓国スタディツアーで、学生と教員の私が気づいたこと
* 連載第7回 孤独と向き合って自分を知った大学生と、これからの社会のありかた
* 連載第8回 ダイバーシティ&インクルージョンに必要な「エンパワメント」と「当事者性」
* 連載第9回 “コミュニケーションと相互理解の壁”を乗り越えて、組織が発展するために
* 連載第10回「あたりまえ」が「あたりまえではない」時代の、学生と大学と企業の姿勢
* 連載第11回「自由時間の充実」が仕事への活力を生み、個人と企業を成長させていく
* 連載第12回 “自律”と“能動”――いま、大学の教育と、企業の人材育成で必要なこと
* 連載第13回 特別支援学校の校長を務めた私が考える、“教え方と働き方”の理想像
特別支援学校の生徒が授業を通して考えたこと
昨年末(2023年末)、新卒入社の内定者向けメディア「フレッシャーズ・コース2025」に、「働くこととキャリア」というテーマで寄稿した。そのときに私が考えたことを、寄稿の内容とあまり被らないように、ここでも書いておきたい。
私は、今年(2024年)の3月で神戸大学附属特別支援学校の校長を退任したが、退任間際にまたひとつ、同校の誇りと思える授業の展開に立ち会うことができた。中学部の授業で取り組まれた演劇教育で、先生たちが、「この授業を受ける子どもたちに適した題材はなんだろうか?」と深く議論した末に選んだのは、昔話の「鶴女房」であった。考えを深めたり、仲間を思いやったりする力はあるものの、他者の気持ちを受け入れたうえで自分を表現するのが苦手――「鶴女房」は、そんな生徒たちが、役柄を演じながら、「なぜ、登場人物はこのような行動をとったのだろうか?」という問いを持つ物語だった。
生徒たちは、まず、主人公の若者が鶴の化身と出会い、恋に落ちていく様子を熱心に演じた。そして、恋することの不思議さや恥じらいや憧れを熱演したからこそ、それに続くストーリーで悩んでいった。悩んだ部分は、「貧しい家で暮らす二人の生計を助けるため、鶴女房が自らの羽で反物を織り、若者がその反物を手に町に行くと、思いがけない高額で反物を売ることができた」というくだりである。味を占めた若者は、鶴女房に反物を織るよう繰り返し懇願し、ぜいたくを楽しむようになっていくのだが、生徒たちは、「なぜ、あんなに愛し合っていたのに、若者は鶴女房を苦しめ、鶴女房は若者のもとを去ってしまったのだろう?」という疑問を抱いた。
先生たちが「若者はダメ男だったのかな?」と問いかけたところ、生徒たちは「その考えは嫌だ」と返した。ダメな人間だから堕落したという短絡的な答えが腑に落ちなかったのである。生徒たちは、正常な判断ができなくなっていく若者の必然性を描きたいと感じたのだろう。彼ら彼女たちが出した答えは、「鶴女房を幸せにしたかったからこそ、若者は不自由のない結婚生活を求め、ぜいたくに身を任せるようになってしまった」というものだった。
生徒たちは、納得のいくストーリーになるまで議論を重ね、その議論の結果を演劇に反映していった。半年にわたる演劇教育だったが、先生たちは、生徒たちが話し合い、試行錯誤を繰り返す様子をていねいに動画に収めていった。
ストーリーは、主人公の若者が約束を破って鶴女房に去られてしまう結末だが、完成した作品の中心的なテーマは、鶴女房に対する若者の細やかな愛情だった。生徒たちが夫婦の愛情を演じたからこそ、鶴女房の別れの切なさが際立った。