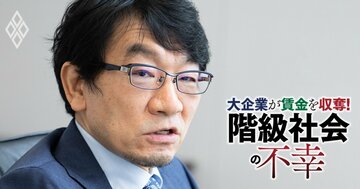Photo:123RF
Photo:123RF
スキマ時間に働けるスポットワーク(いわゆるスキマバイト)」市場が急速に拡大する一方で、それに伴い、ワーカーが労務トラブルに巻き込まれるケースも急増している。スキマバイトの現場では何が起きているのか。特集『スキマバイト 光と影』の#6では、東京都内にある18の労働基準監督署を管轄する東京労働局に、トラブルの実態や背景を聞いた。(ダイヤモンド編集部編集長 浅島亮子)
爆発的拡大を見せるスキマバイトに
労務リスクの影
短時間・単発で働ける「スポットワーク(いわゆるスキマバイト)」市場が、いま爆発的な拡大を見せている。アプリ一つで即日勤務が可能という利便性から、登録会員数が3200万人まで拡大している。
その爆発的成長の裏側で、都合の良い労働法制・ルールの解釈や運用行われており、現場では、さまざまな労務トラブルが顕在化している。
スポットワークでは、ワーカーと企業をマッチング(職業紹介等)する「スポットワーク仲介事業者(タイミー、シェアフルなどのプラットフォーマー)」と、ワーカーに仕事を提供する「利用企業」というプレイヤーが存在する。本来、ワーカーの「労働基準法上の雇用主」は利用企業であり、スポットワーク仲介事業者ではない。
しかし現実には、スポットワーク仲介事業者による説明が不十分であることに加え、利用企業の理解不足も重なり、多くのワーカーが、「自分が誰に雇われているのか」を正しく認識できていない。その結果、賃金の未払いや労働条件の不備といったトラブルが多発。ワーカーが労働基準監督署へ駆け込む事例が増加している。
ここで強調しておきたいのは、スポットワーカーも労働法上は一般の労働者と同じ扱いである点だ。たとえ就業時間が短くとも、賃金や安全衛生など労働者としての権利は等しく適用されるのだ。
では、スポットワーク現場ではどのような労務トラブルが起きているのか。スポットワークが最も浸透している首都圏である。18の労働基準監督署を管轄する東京労働局の神子沢啓司・労働基準部監督課長に、その実態を聞いた。
次ページでは、スポットワークの現場で浮かび上がった労務トラブル「6つの重大ケース」を取り上げる。