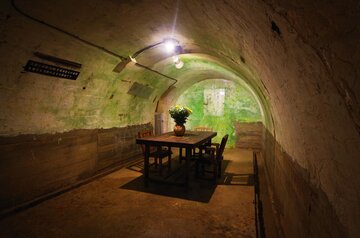服部半蔵が、リーダーとしての
力を発揮できなかった理由
ではなぜ情報を生かせず、戦略を描けなかったのか。それが失敗の要因の第三、指導者の欠如である。
伊賀や甲賀には、統治能力に優れた人物も多くいた。伊賀ではのちに徳川家康のもとで大身旗本となる服部半蔵(正成)や、甲賀では織田家重臣の滝川一益、摂津の守護にまでなる和田惟政などを輩出しているのである。
ところが、彼らは自分たちの郷土ではなく他家に移ってから幹部になっていく。伊賀では十二家、甲賀では五十四家がその指導的立場にあり、合議制で物事は決められていた。つまり突出したリーダーではなく調整能力と権威が優先された。
その結果、たとえば伊賀をそれまでの「同業者組合」から、群小勢力を合併によって「事業部制の企業集団」に転換するような動きはなかった。
「時代の転換期、我らはこうやって未来を拓く」という戦略的号令をかけるものがなく、有能な人材をかなりの数かかえながら、しかも京や大坂に近い好立地でありながら、ついに異能集団は自分たちの未来を切り拓けなかった。
ではどうするべきであったのか。情報によって時代の趨勢を読み取り、変化の中で自分たちの得意分野を生かすにはどう動くべきかを見極め行動すべきであったろう。
具体的には、織豊政権が望んだ国際交易に生かせる海外情報や海外人脈、鉱山技術に関する先進的な情報、政権に謀反を起こす可能性のある大名家への監視強化とその報告など、時代の新たな構造の中でも十分生き残ることはできた。
現に徳川幕府に雇用された伊賀・甲賀の後裔たちは、「お庭番」など情報収集や大名監視で活躍し、あるいは鉄砲隊や江戸城警備要員として「伊賀組」「甲賀組」「根来組」などが組織されたのである。