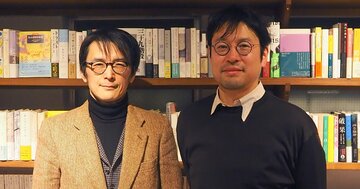ポイント(5)ボブ・マーリーの交友関係
平和のための音楽と政治利用される音楽
10代のボブは、幼なじみのバニー・ウェイラーと、トレンチタウンに住み始めてから出会ったピーター・トッシュと共に、音楽活動を本格化。6人組の「ザ・ティーンエイジャーズ」を結成する。ボブは母親が歌っていたゴスペルに影響を受けており、独特な歌詞とハーモニーを売りにしたボーカルグループとして注目される。その後、「ザ・ウェイリング・ウェイラーズ」、そして「ザ・ウェイラーズ」へと名称を変更した。
1963年、スタジオ・ワンから発表した「Simmer Down」が大ヒット。この頃、同じくスタジオ・ワンに在籍していたグループのメンバー、リタ・アンダーソンと出会い、結婚する。
曲がヒットしてもミュージシャン側にはほとんどお金が入ってこず、アメリカの自動車工場のライン工やレストランの皿洗いなどをして生活費を工面していた。ジャマイカに帰国後、稼いだ資金で自らレーベルを開始するが、すぐに経営難となって消滅した。
その間も次々と曲を発表するが、この頃、バンドの音楽に大きな影響を与えることとなる人物たちと出会う。スタジオ・ワンのエンジニアであり、ミュージシャンのリー・“スクラッチ”・ペリーと、そのスタジオバンドのザ・アップセッターズだ。ザ・アップセッターズのメンバー2人がザ・ウェイラーズに加わり、彼らの音楽の完成度が飛躍的に高まった。
音楽プロデューサーと反りが合わなかったとか、ボブを前面に押し出す方針に気が乗らなかったとか、諸説あるようだが、1974年、ピーター・トッシュが脱退。続いてバニー・ウェイラーも脱退してしまう。ボブはメイン・ボーカルとなり、ザ・ウェイラーズはメンバーを交代しながらバックバンドを務め、「ボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズ」という編成ができあがる。
ボブは、スティービー・ワンダーの慈善コンサートに参加し、これに感化されて、1976年に「スマイル・ジャマイカ・コンサート」を開催することにした。二大政党の対立が激化しており、政治を巡っての銃殺事件も日常茶飯事に起きていた。子どもたちでさえ標的にされ、惨状を見かねた多くの医師が国を離れた。そのため、音楽でジャマイカ国内に笑顔をもたらそうと企画したチャリティコンサートだった。
しかし開催日が近づくにつれて脅迫が相次ぐ。政府が協賛し、しかも与党のPNPがコンサート開催の直後に総選挙を行うことを発表。ボブらが制作したジャマイカ賛歌「スマイル・ジャマイカ」が繰り返しラジオで流れた。当然、PNPに敵対するJLPの支持者は、コンサートは与党の宣伝のために開催されると思い込んだ。ボブは戸惑い、開催に否定的なメンバーもいた。
そして開催の2日前、事件が起こった。武装した6人がリハーサル中のボブたちを襲撃し、マネージャーのドン・テイラーに5発撃ち込まれる。ボブも左胸に撃ち込まれた。建物の外で車に乗っていたリタも撃たれ、頭部に命中したが、ガラスを通ったこととドレッドヘアが、弾の勢いを弱めた。幸い3人とも命に別条はなく、ボブは2日後のコンサートにも出演。傷のためギターを弾くことはできなかったが、約90分のライブを完遂した。
その後、このままジャマイカにいては命を落としかねないと考えたボブは、イギリスへ活動の拠点を移し、しばらく制作活動に注力する。当時流行していたパンクシーンも直接、体験した。そこに、ジャマイカから2人の人物が訪ねてくる。PNPのガンマンであるバッキー・マーシャルと、JLPの幹部のクローディー・マソップだ。
2人は対立する政党に所属していたが、お互いにボブの友人であったことから刑務所内で意気投合。ジャマイカでは、政党間の抗争の激化、市民戦争、軍部によるクーデターなどが現実味を帯び始め、内乱に陥る寸前だった。そこで、キングストンで開催される平和をテーマにした「ワン・ラブ・ピース・コンサート」にボブに出演してもらい、国民の団結をはかってもらいたいとボブに訴えた。そのため、ボブをジャマイカに連れ戻しに来たのだ。
ボブは、自身やリタが襲撃された経験から悩んだが、1978年、ジャマイカに帰国し、ザ・ウェイラーズと共にコンサートに出演。満員の聴衆の中、ボブはコンサートを訪れていたPNPの党首であり首相のマイケル・マンリーと、JLPの党首であるエドワード・シアガの2人をステージ上に招き、和解の握手をさせる。このシーンは伝説となった。
なお、オリジナルメンバーのピーター・トッシュは、ザ・ウェイラーズ脱退後も、レゲエの重要人物として活躍し続けたが、1987年に強盗に射殺されてしまう。相手は幼なじみだった。バニー・ウェラーは、米グラミー賞の最優秀レゲエアルバム賞を3度受賞するなど多くの功績を残し、2021年、73歳で病没した。
ダブのパイオニアでもある、リー・ペリーは、近年までミュージシャン、プロデューサーとして活躍し、世界中のさまざまなミュージシャンに影響を与えた。日本にも熱狂的なファンが多く、何度も来日している。2021年、85歳で死去した。
JLPのクローディー・マソップは、「ワン・ラブ・ピース・コンサート」の8カ月後、警官に車を降ろされ射殺された。PNPのバッキー・マーシャルは、1980年に路上の音楽イベントに参加中に何者かに銃殺された。
ポイント(6)ボブ・マーリーと子どもたち
ボブ・マーリー家はレゲエ界のロイヤルファミリー
ボブが21歳、リタが19歳のときにリタと結婚。結婚時、リタは娘を育てており、ボブは養子として迎え入れた。ボブとリアの間には4人の子ができたほか、ボブはリタ以外の複数の女性とも子をもうけている。また、リタもボブ以外の男性と子をもうけ、ボブはその子も養子に迎えている。
ボブには、養子含め公式には11人、それ以外にも7人ほどの子どもがいるとされる。その中には歌手として活躍する子も多く、「レゲエ界のロイヤルファミリー」と呼ばれている。ボブとリタは(互いの男女関係について何度もトラブルはあったようだが)離婚せずに、生涯、夫婦であり続け、すべての子を大切に育てたという。
ポイント(7)ラスタファリ運動
ボブ・マーリーの曲が世界中で愛されている理由
レゲエミュージックが好きな人は、「ラスタ」「ラスタファーライ」や「ジャー」といったことばが曲の中にちりばめられていることを知っているだろう。これらの言葉は「ラスタファリ」という宗教的な概念に基づく。
この概念が非常にややこしいのである。さまざまな説が入り乱れている上に、日本に住んでいる私たちの感覚では理解が難しい。本作の中でもこの概念に基づく描写が多く登場するので、「?」となるシーンもあるだろう。
ラスタファリの発祥は、1924年にカリブ海のアンギラ出身者によって書かれた『ホーリー・ピビィ』という本が「黒人の聖書」として広まり、ラスタファリの誕生へとつながったという説や、黒人指導者のマーカス・ガーヴェイ(1887年〜1940年)が提唱したという説などがあり、よくわかっていない。ただ、ボブの妻のリタは自伝の中で、ラスタファリは20世紀初頭にガーヴェイが始めたと語っているので、ボブたちがガーヴェイから多大な影響を受けたことは間違いない。
ガーヴェイはボブと同じセント・アン出身で、ニューヨークへ渡り、「世界黒人地位改善協会」を設立。黒人としての誇りを持とう、黒人たちはアフリカへ帰還しよう、と主張した。そして「アフリカの王が、世界の植民地を解放する」「救世主が現れてアフリカ大陸を統一し、奴隷として世界中に離散した黒人たちを約束の地であるアフリカへと導いてくれる」と予言する。この救世主を「ヤハウェ」と呼んだ。
ヤハウェとは、旧約聖書や新約聖書における、唯一絶対の創造神のことであり、短縮して「ヤー(ジャー)」と呼ぶ。「Hallelujah(ハレルヤ)」は、ヘブライ語で「ヤーをたたえよ」という意味。レゲエの曲に多く登場する「ジャー」という言葉は、黒人を導く神を誉め讃えているのだ。
アフリカのエチオピアは、1894年〜1896年、植民地化を狙うイタリアと戦い、これを撃退した(第1次エチオピア戦争)。1935年〜1936年、復讐心に燃えるイタリアは再度、エチオピアに侵攻し、エチオピアをイタリア領とした(第2次エチオピア戦争)。しかし、第2次世界大戦勃発後の1941年、イギリス軍がイタリア軍を駆逐すると、再びエチオピアは独立、軍の近代化を進める。
こうした背景(国として長い歴史を有すること、欧州相手に勝利したこと、アフリカ諸国の中でほとんど植民地化されなかったこと、エチオピア皇帝が再び返り咲いたことなど)が影響して、「ガーヴェイの予言は的中した」「エチオピア皇帝こそが、ガーヴェイが予言した王だ」「エチオピア皇帝は我々をアフリカへと導いてくれる救世主だ、神(ジャー)の化身だ」と、多くのジャマイカ人へガーヴェイの思想は波及していった。
このエチオピア皇帝の名はハイレ・セラシエ1世(1930年4月に即位)といい、本名を「ラス・タファリ」という。そこからラス・タファリを崇拝する人々を「ラスタファリアン」「ラスタ」と呼ぶようになっていく。
ラスタは、体を一種の聖堂とみなし、旧約聖書の「レビ記」の教えを守り、髪を切ったり、くしを入れたり、ひげを剃ったりすることはしない。頭髪を自然に成長するままとし、伸びた髪はまとめて「ドレッド・ロックス」と呼ばれる髪形にする。
「ドレッド」という言葉は「ひどい」「恐れる」「畏れる」という意味があるらしく、植民地時代のジャマイカで、支配者、つまり、「ひどい」やつらへの抵抗を示した髪形なんだという意見や、見るものが「恐れる」ほど勇敢なジャマイカの戦士たちという意味だという意見や、自然や聖なる存在を「畏れる」という意味だという意見などがあり、由来はわかっていない。
ラスタの中にもさまざまなタイプがいるが、基本的に菜食主義であり、大麻を神聖な植物とする。当初、怪しい異端の宗教として嫌われ、警察も取り締まった。しかしボブの登場で、ラスタの文化は急速に大衆の支持を獲得していった。
なお、ラスタの人たちは「ラスタファリズム(ラスタファリ教)」と呼ばれることを好まない。自分たちが実践しているのは宗教ではなく、あくまで「ラスタファリ」という、心の状態や生き方そのものなのだと考える。
聖書を原理主義的に解釈する者の中に、同性愛を否定する者もいるが、ボブの歌にはそのような記述は見当たらない。また、黒人以外を認めないという極端な黒人至上主義者もいるが、白人と黒人との間に生まれたボブは人種の優劣を主張することはしていない。差別されている黒人の地位を向上させ、どの人種もフラットな立場にする、それがボブの願いであり、彼の曲が世界中で現代にいたるまで愛されている理由であろう。
ポイント(8)ボブ・マーリーの最後
死因はがん、国葬が執り行われた
1977年、ボブはヨーロッパツアー中にサッカーをしていた(ボブはサッカーの熱狂的なファンであり、よくコンサート前にサッカーをして体力をつけていた。技術も相当高く、プロ・サッカー選手になることも真剣に考えていた時期があったという)。その際、足の親指を負傷し、ツアーが終わった後も治るどころか悪化し、膿んでしまう。
気分がすぐれない日が続き、医者に検査してもらったところ、膿からがん細胞が検出される。医者は足の一部をすぐに切断することを勧めたが、敬虔なラスタであったボブは、体に刃物を当てることに強い抵抗を示し、これを拒否した。
足を切断せずに爪をはがして応急処置を行うことで、一時的に体調はよくなったが、1980年に再び悪化。放射線療法を開始し、治療のためドレッドも抜け落ちたが、すでにがんは全身に転移していた。1981年5月11日、家族に見守られながら息を引き取った。36歳だった。
遺体は5月19日にジャマイカへ送られ、21日にキングストンで国葬が行われた。リタは抜け落ちたドレッドをカツラにして、それをボブの頭にかぶせたという。葬儀の前には、ザ・ウェイラーズのメンバーによる演奏が行われた。ひつぎはその後、ボブの故郷のナイン・マイルズに運ばれ、ジャマイカの全人口の約半数もの人々が村を訪れ、弔慰を示した。