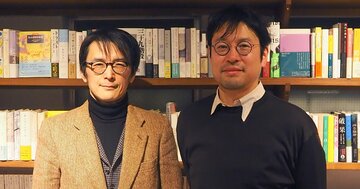ポイント(9)押さえておきたい曲
「One Love」
1965年に発表。「手を取り合って、楽しくやろう」というラスタの基本哲学を反映した曲。初めて発表されたのは1965年、ボブが所属していたコーラスグループのアルバムにおいてだった。その後、ボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズの1977年のアルバム『Exodus』に収録され、1984年にシングルとして発売された。カーティス・メイフィールドが在籍したインプレッションズの「People Get Ready」のメロディを一部引用しているため、1977年以降、「One Love/People Get Ready」と併記されている。
「No Woman, No Cry」
トレンチ・タウンでの貧しい生活の体験をもとにした名曲。ザ・ウェイラーズの1974年のアルバム『Natty Dread』に収録。その後、1975年7月にイギリス・ロンドンのライシアム・シアターで行われたコンサートのライブ音源をシングルとして発売したところ、大ヒット。ジャマイカ以外で初めてヒットした曲となった。数多くのミュージシャンにカバーされている。なお、この曲の作詞・作曲は「ヴィンセント・フォード」とクレジットされている。ヴィンセントは、ボブのトレンチタウン時代の友人で、貧しかったために病気の治療を受けられず足を失い、車椅子での生活を送っていたという。ヴィンセントはトレンチタウンで炊き出し所を営み、当時、路上生活をしていたボブも、彼の炊き出しによって飢えずにすんだ。その感謝を込めて、彼に印税が入るようにクレジットしたというエピソードがあるが、真相は定かではない。レゲエというのは、何気ない会話から生まれたり、1曲ができるまでに非常に多くの人が関わったりすることは珍しくないので、権利関係が複雑になることも多い。
「Exodus」
襲撃事件後、イギリスへ渡ってレコーディングした1977年のアルバム『Exodus』に収録された曲。Exodusとは、旧約聖書の「出エジプト記」のことで、モーゼに導かれたイスラエルの民がエジプトから旅立つ記述と、ラスタの人々がアフリカに帰ることを結びつけている。
「Get Up, Stand Up」
1973年のアルバム『Burnin’』に収録された曲。権利のために立ち上がれ、自由のために戦い続けよう、と呼びかける。全員が同じメロディを一斉に歌うチャント(キリスト教の教会の儀式のときに歌われる聖歌)のように、同じメッセージが繰り返される。コンサートの最後に歌われることが多かった。
「Punky Reggae Party」
1970年代、イギリスでパンクのムーブメントが起こる。パンクの代表格、セックス・ピストルズやクラッシュのメンバーは、レゲエへのリスペクトを公言し、ボブたちもまたパンクに刺激を受け、それに応える曲をつくった。クラッシュの曲『Complete Control』をプロデュースしたばかりのリー・ペリーと一緒に制作した曲。
「War」
1976年のアルバム『Rastaman Vibration』に収録された曲。人種差別がなくなるまで、基本的人権が平等に保障されるまで、アフリカ大陸に平和が訪れるまで、戦い続ける、という歌詞で、過激に聞こえるが、国際連合でハイレ・セラシエ1世がアフリカ諸国の独立を訴えた演説をもとにしている。
参考文献:
『BOB MARLEY songs of freedom』(ブルース・インターアクションズ、監修:リタ・マーリー監修、写真:エイドリアン・ブート、文・クリス・サレウィッチ、訳:中江昌彦)
『ボブ・マーリー』(偕成社、著者:マーシャ・ブロンソン、訳:五味悦子)
『ボブ・マーリーとともに』(河出書房新社、著者:リタ・マーリー+ヘッティ・ジョーンズ、訳:山川真理、越膳こずえ、島田陽子)
『ボブ・マーリィ キャッチ・ア・ファイア』(音楽之友社、著者:ティモシー・ホワイト、訳:青木誠)
『ボブ・マーリー レゲエの伝説』(晶文社、著者:スティーヴン・デイヴィス、訳:大橋悦子)
■監督:レイナルド・マーカス・グリーン
■出演:キングズリー・ベン=アディル、ラシャーナ・リンチ
■脚本:テレンス・ウィンター、フランク・E ・フラワーズ、ザック・ベイリン、レイナルド・マーカス・グリーン
■全米公開:2024年2月14日
■日本公開:2024年5月17日
■原題:Bob Marley: One Love
■配給:東和ピクチャーズ