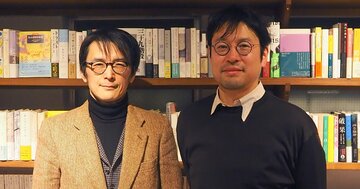ポイント(2)ジャマイカの政治
殺人も多発する二大政党の争い
イギリス統治下の時代、ジャマイカの黒人たちは、何度も反乱を起こし、中には1865年の「ジャマイカ事件」のような、数百人規模の大規模な暴動もあった。
イギリス領西インド諸島での奴隷解放運動の高まりによって、1834年に奴隷制廃止令が発令し、それに基づいて1838年に奴隷制度が廃止。ジャマイカの奴隷は解放され、選挙権も得たはずだったが、選挙の投票は高額で、投票できるのはほとんどが白人であり、事実上、黒人には参政権のない状態だった。黒人の身分はほぼ奴隷時代のままで、変わらず極貧生活を強いられた。
1938年、民主社会主義を掲げる人民国家党(PNP/People's National Party)が設立。イギリス領カリブ圏諸国の最古の政党といわれている。また、1943年には、労働条件の改善などの社会改革を求めるジャマイカ労働党(JLP/Jamaica Labour Party)が設立される。現在、この2つがジャマイカの二大政党であり、期間は違えど交互に政権が入れ替わる状態が続いている。映画ではこのあたりもポイントとなってくる。
1959年に、ジャマイカはイギリスから自治権を獲得し、1962年、ついに独立を果たす。ただ、主権国家とはいえ、イギリス連邦の加盟国のため、独自の元首を持たない。イギリス国王を国家元首とし、現在はイギリス国王のチャールズ3世がジャマイカ国王を兼位しているが、象徴的な存在であり、今は実権をほとんど持たない。
2011年10月、JLPよりジャマイカ政治史上最年少(当時39歳)のアンドリュー・ホルネスが首相に就任。その直後の12月の総選挙ではPNPが勝利し、シンプソン=ミラーが首相に就任する。2016年2月の総選挙で今度はJLPが勝利し、ホルネス政権が返り咲く。2020年9月の総選挙でも与党JLPが勝利し、ホルネス首相が再任。現在に至る。
なお、この二大政党の支持者たちの対立は苛烈で、選挙期間中に観光客などがジャマイカ二大政党のイメージカラー(JLPは緑、PNPはオレンジ)の衣服を着用していると、襲撃などのトラブルに遭う可能性があり、日本の外務省もWebサイト等で注意喚起している。
ポイント(3)ボブ・マーリーの誕生
白人と黒人の間に生まれたことを悩む
本映画の主人公であるボブ・マーリーは、1945年、丘陵部のセント・アン教区内のナイン・マイルズという村で生まれた。
父親の名はノーバル・マーリー。ジャマイカに住む白人で、イギリス海軍の西インド諸島連隊で将校を務めていた。また、建設会社のオーナーでもあった。
ノーバル・マーリーは、自身の担当地域に住むセデルラと出会い、間もなくセデルラは子を身ごもった。のちのボブ・マーリーだ。ノーバル・マーリーの家は代々、黒人嫌いで有名で、また、2人は40歳以上も年が離れていたことから、セデルラの母親は2人の結婚をひどく反対したが、ノーバル・マーリーが馬に乗って現れ、セデルラの母親に直接、2人の結婚を申し込むと、ようやく認めたという。しかし、黒人との結婚に腹を立てた家族と関係がこじれ、挙式後、ノーバル・マーリーは、首都のキングストンへ働きに出て行った。
1945年に誕生したノーバルとセデルラの子は、父親の兄弟の名前をもらって「ロバート」と名づけられた。セデルラはミドルネームに「ネスタ」をつけた(「使者」という意味があるらしい)。ロバートは、英語圏では「ボブ」の愛称で呼ばれることが多い。そのため、ロバート・ネスト・マーリーは、「ボブ・マーリー」と呼ばれるようになる。
ボブ・マーリーという名前だけでも、白人とジャマイカ黒人という人種や文化の違いが込められているように、ボブは若い頃、自身のアイディンティティに悩み、苦しんだ。家族を放ったらかしにしてほとんど現れない父親を恨み、生い立ちに口を閉ざし、「自分や一族はアフリカから来たのだ」と語るようになった。その謎に満ちた一面から、神秘的な雰囲気をまとうようになっていく。
1955年、父が70歳で亡くなると、両家の縁は切れ、生活が厳しいセデルラとボブは、キングストン郊外のスラム、トレンチタウンの公営地で住み始める。トレンチタウンは治安が劣悪なエリアであり、現在も観光客が近づくのは大変危険とされる。一方で多くのレゲエミュージシャンを輩出し、ボブもこの街での生活が強く印象に残ったようで、ボブの歌の中でも「トレンチタウン」というキーワードが頻出する。
ポイント(4)レゲエの誕生
カリブの音楽の中でもっとも世界へ普及
レゲエはジャマイカのソウル・ミュージックだ。バーを宣伝するために音楽を大音量で流したことから、現在のレゲエのスタイルが始まったといわれている。
もとは、宗主国のヨーロッパの音楽の要素と、黒人音楽といわれる、ゴスペルやジャズ、R&B、ロックといったさまざまな音楽の要素に、熱く燃えるようなアフリカのドラムの響きが加わり、原型が形作られていった。
そして、アップテンポな「スカ」(1950年代後半にブーム)、スカからテンポを落とした「ロックステディ」(1966年頃からブーム)を経由し、ロックステディからさらにテンポを落とした「レゲエ」が1960年代後半に生まれた。2拍目と4拍目をドラムで強く打つ独特のリズムと、けんか腰で挑戦的な歌詞が特徴だ。
ジャマイカの二大音楽レーベル、「スタジオ・ワン」のコクソン・トッドと、「トレジャー・アイル」のデューク・リード(つねに銃を2丁携帯し、ギャング集団を護衛につけた武闘派だった)はどちらもバーを経営していて、自分のレーベルの曲を中心に、ライバルに負けないように大音量で流した。
サウンドシステムにもとてもこだわった。サウンドシステムというのは、巨大なスピーカーを備えた音響機器そのものをさすこともあれば、DJやミュージシャンたちの集団をさすこともある。ときには機材を車に積み込んで島内を巡り、屋外ディスコのようにガンガン音楽を流してレコードを売って回った。なお、レゲエのDJは「セレクター」や「dee jay」とも呼ばれ、マイクで話しながら曲を流すことも多い。
レゲエは、貧困や差別、政治的抑圧を訴えかけたり、ラスタ(後述)の思想にも影響を受けたりと、社会的なメッセージが込められるようになっていった。
初めは、ジャマイカに住む白人たちはレゲエに対し、「無教養な黒人の音楽」「単調な西インド諸島の音楽」とさげすんだ。白人だけでなく、否定的な態度を示す黒人も多かったが、次第にジャマイカの若者を中心に広まり、やがてボブたちによって、世界中で受け入れられるようになっていった。
なお、カリブ全体でもっとも人気の高い音楽は「ソカ」であり、レゲエというわけではない。しかし、レゲエはカリブが生んだ音楽の中で、もっとも世界に広まった音楽といえる。宗主国だったイギリスからヨーロッパやアメリカに広がり、アフリカでも音楽好きのみならず、ラスタに共感して聞く人も多い。不思議なことに、ジャマイカとの歴史的・文化的なつながりがほとんどないにもかかわらず、アジアにおけるレゲエ大国といわれるほど、日本でも人気が高い。
レゲエをベースとしたインストゥルメンタルの「ダブ」や、ノリがよく情熱的・官能的な歌詞が特徴の「ダンスホール・レゲエ」といったジャンルも生まれている。