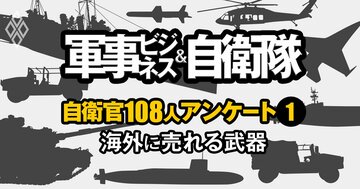写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
ロシアのウクライナ侵攻報道などで度々耳にする民間軍事会社。中でもロシアの民間軍事会社「ワグネル」は、創設者であるプリゴジン氏が亡くなったことが大きな話題となった。しかし、そもそも民間軍事会社とは、一体どのような組織なのだろうか。※本稿は、菅原出著『民間軍事会社 「戦争サービス業」の変遷と現在地』(平凡社新書)を一部抜粋・編集したものです。
民間軍事会社の定義はなく
権限などを規定する法律もなし
「ロシアの民間軍事会社ワグネルの戦闘員が……」というように日本のメディアでも「民間軍事会社」という用語が頻繁に使われるようになった。
「民間」の「会社」なのに「軍事」と関係している……。これは「戦争を商売にしている会社」「民間人を戦場に送り戦闘に従事させることで利益を得ている会社」という印象を抱かせる名称である。他にも「傭兵会社」といった呼び方もしばしば耳にする。
「民間軍事会社」とはいったい何だろうか?
結論から言えば、国際的に確立された定義はない。「警備会社」であれば、通常警備事業法のような法律があり、警備業に当たる業務に関する細かな規定が存在する。国の認定する資格を取得して事業を行うことを認められた会社が「警備会社」を名乗ることが出来るのだ。すなわち「警備会社」が何であるかが法的に明確に定められている。
同じような法的なステータスは「民間軍事会社」にはない。つまり「民間軍事会社」が何であるか、その業務内容や権限等を規定した法律が存在しないのだ。
2008年9月17日にスイスのモントルーで採択された「モントルー文書」で規定された定義が、おそらくこれまででもっとも公的な性格を持つものであろう。
このモントルー文書は、スイス政府と赤十字国際委員会が協力して開始した取り組みの成果で、紛争地帯で活動する民間軍事会社の行動に関して定めたものだ。2006年1月と11月、2007年11月、2008年4月と9月に開催された会議で、アフガニスタン、アンゴラ、オーストラリア、オーストリア、カナダ、中国、フランス、ドイツ、イラク、ポーランド、シエラレオネ、南アフリカ、スウェーデン、スイス、英国、ウクライナ、米国から政府専門家を集めて作成され、市民社会や民間軍事・セキュリティ産業の代表者の意見も取り入れてまとめられた。
だがこの文書には法的拘束力はなく、国際慣習法にも国際協定に基づく国家の既存の義務にも何ら影響を及ぼすものではない。
モントルー文書は、「民間軍事警備会社(private military and security companies:略称PMSCs)」という名称を使い、「PMSCsとは、軍事及び安全保障サービスを提供する民間の事業体であり、軍事及び安全保障サービスには、車列や建物や他の施設の武装警備、人及び物の防護、武器システムの保守・運用、囚人の警護、現地の軍隊や治安部隊に対する助言や訓練も含まれる」としている。