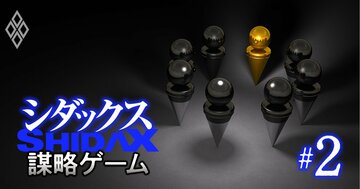この一連の経緯から、上場企業はこぞって平時から買収防衛策を導入するようになります。買収防衛策の具体的な制度設計をするのは弁護士事務所で、当時は一件につき2000~3000万円のフィー(手数料)を取ると言われていました。ピークである2008年には570社が導入済みとの統計もあります。おかげで弁護士業界は大儲けをしたことでしょう。
「防衛」したいのは
企業ではなく経営者の地位?
2023年8月末、経済産業省は「企業買収における行動指針」(以下「指針」)を公表しました。そこでは、買収防衛策の目的について以下のように記しています。
買収への対応方針が適切に用いられる場合には、株主に検討のための十分な情報や時間を提供するとともに、取締役会に買収者に対する交渉力を付与し、買収者や第三者からより良い買収条件を引き出すことを通じて、株主共同の利益や透明性の確保に寄与する可能性もある。
つまり買収防衛策の目的は、株主共同の利益の確保にあります(傍線筆者)。そのために買収者から情報提供を受け、是非を検討する時間を確保することで、買収条件を改善できるような交渉力を獲得しようというわけです。
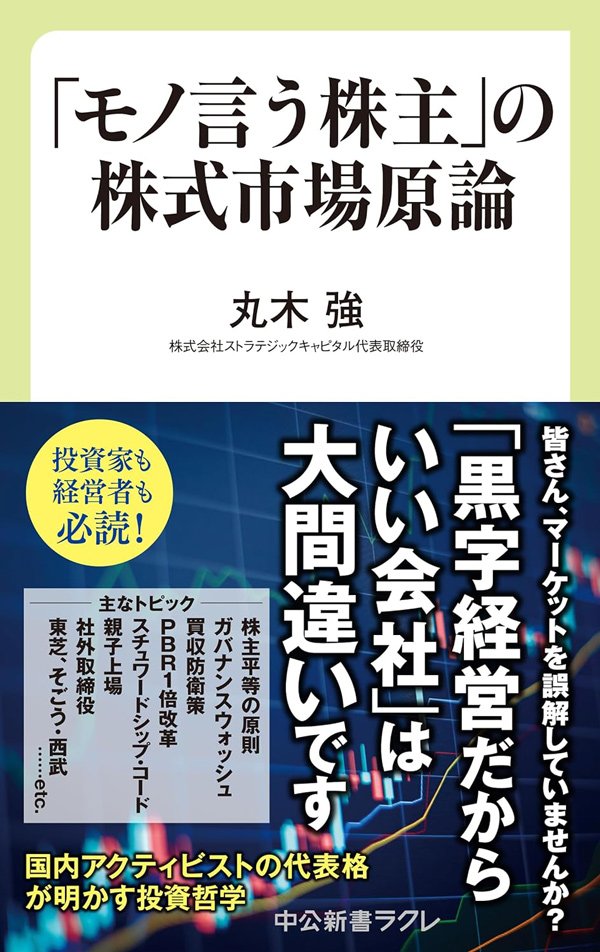 『「モノ言う株主」の株式市場原論』(中公新書ラクレ) 丸木 強 著
『「モノ言う株主」の株式市場原論』(中公新書ラクレ) 丸木 強 著
買収者が現れたとき、その提案が既存の一般株主にとってプラスかマイナスか、ただちには判断できないことがあります。そこで情報を収集したり、買収者に質問状を送ったりして検討するわけですが、その時間を確保するための手段という位置づけです。あくまでも、買収提案が既存株主の利益になるか否かを判断することが目的のはずなのです。
ところが今までの日本では、買収防衛策は単純に買収を妨害するための道具になっていたのではないでしょうか。つまりは一般株主の利益のためではなく、経営者の保身のためでしかないわけです。
例えば2008年、日本電産(現・ニデック)が東洋電機製造に買収を持ちかけたことが話題になりました。日本電産側は市場価格の2倍を提示して東洋電機株のTOBを提案。しかし東洋電機側はすでに導入していた買収防衛策の一環として、日本電産側に質問状を送付します。そのやりとりが何度となく繰り返されるうちに提案期限を迎え、日本電産は撤退しました。これが東洋電機の株主の利益にかなうものだったのか否かは、はなはだ疑問です。