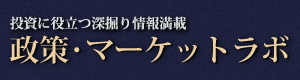注意すべき第一は、当然のことだが、上記の意味での「壁」を完全になくすことはできないということだ。所得が増えれば、どこかで所得税がかかってくる。
第二に、103万円が壁だというのは給与所得の場合であって、他の形態の所得の場合には、壁はこれとは異なる額になり得る。例えば雑所得であれば、給与所得における経費(基礎控除)以上の経費が発生する場合もあるだろうから、壁はもっと大きな値になることもあるだろう。
第三に、「年収の壁」と言われるものは、これ以外にもいくつかのものがある。扶養控除の適用がなくなるので世帯主の税負担が多くなるという壁、社会保険の保険料の納付義務が生じる「106万円」や「130万円」の壁などだ。
だから、103万円の壁を引き上げたところで、就業時間に対する影響がなくなるわけではない。実際には、配偶者控除や社会保険の加入に関連した壁のほうが、就労の制限になっている場合が多いのではないだろうか。
第四に注意すべきは、インフレに対して所得税制を中立化する必要は、基礎控除の調整だけではないことだ。もう一つの重要な課題として累進税率構造の調整がある。
所得税は累進構造になっているため、名目所得が増加すれば、税率は自動的に上昇してしまう。これが前回本コラムで指摘した「ブラケット・クリープ」の問題だ。
いま年収の壁として問題となるのは、就業時間が固定されていない場合だ。年間の所得が100万円近辺の納税者の問題であり、主としてパートタイム労働者などの問題だ(ただし基礎控除の引き上げは、高額所得者の税負担をも下げることになる)。
それに対して累進税率の調整の問題は、より広い対象の納税者に大きな影響を与える。
給与所得者で言えば、これによって影響を受ける人々は正規雇用者が中心になる。税収に対する影響という観点からすると、累進税率の上昇のほうが大きな影響を与えるだろう。
年収が100万円程度であれば、基礎控除を調整しても、1人当たりの所得税負担の増額はあまり大きな値ではない。だからこれを調整しても、税引き後の所得が大きく増えるかどうかは疑問だ。それに対して累進構造の調整は税引き後の所得にかなり大きな影響を与え得る。
目的曖昧だった昨年の所得減税、
2025年度税制改正ではじっくり議論を
23年の経済対策には盛り込まれた所得税減税は大きな問題を含むものだった。
「税収増を納税者である国民に分かりやすく『税』の形で直接還元する」とし、22年度までの2年間で所得税・住民税の税収が3.5兆円増えた分を還元すると位置付けた。納税者本人とその扶養家族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円を24年の納税額から控除するのだが、この減税はそもそも、何のために行なったかがはっきりしなかった。
提唱者であった岸田文雄前首相は、「増えた税収を国民に返す」とした。仮にその言葉通りだとしたら、これはインフレに対して所得税制の中立化が必要との発想だ。しかし、そうであれば定額減税ではなく、基礎控除や累進構造の調整などの税制改革を行なうべきだった。
だが定額減税が行なわれ、基礎控除も累進構造も手が付けられていない。所得税制の基本が変わったわけではないのだ。これは1回限りの減税だから、インフレが収まらなければ、税負担が増えてしまうことになる。
実際は、防衛費の増額のために増税を行なうことを決めたことに対して批判が強まり、それへの対処として世論をなだめるためにバラマキ的な減税を行なったとしか考えようがない。
所得税制の構造を変えるという複雑な問題を拙速に決めてしまうべきではない。
慎重な検討を行なうために、25年度の税制改正ではじっくりと議論をすべきだ。
(一橋大学名誉教授 野口悠紀雄)