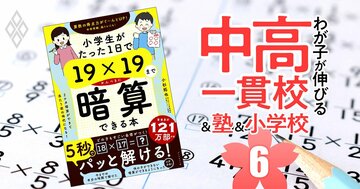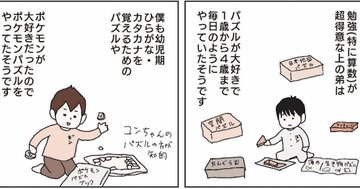問題を解くことが
ゴールではない
一見すると、算数と関連のないジャンルの体験であったとしても、算数の問題を解くために必要な知的好奇心を育むことにつながっていきます。
たとえば、「テレビのドキュメンタリー番組を見て、アマゾンの奥地にはこんな文化があるんだ」ということを知ったとします。「へー!」と子どもの心が動き、「世界には私が想像できないような文化を持つ民族がもっといるのかな?」「ジャングルの奥地では、どんな生活を送っているのだろう?」など、子どもによってさまざまな知的好奇心が湧いていきます。
これまで触れたことのない社会的なことや科学的な事象を知ると、知識欲が刺激されるのです。
このような、さまざまなことを吸収していこうという姿勢は、自分の知らなかった解き方を習得していこうとする算数を学ぶ意欲にもつながります。
興味の幅が広い子どもは、自分が一度解けた問題に対して、別解も探ろうとします。
「こっちもおもしろそうだな!」「他にも方法があるかな?」と興味は数珠つなぎとなっていくのです。
逆に、別解に対して興味を示さない子も多くいます。
別解を楽しめる子は、問題を解くことがゴールになっているのではありません。もっと根源的な知識欲や好奇心に突き動かされていて、自分が楽しいと思うかどうかが重要なのです。けれども、別解に興味のない子は、答えがでるかどうかだけが関心事となっています。
知識欲や知的好奇心を育てていくには、あらゆるジャンルで経験できる「そうなんだ!おもしろいな」「知らないことを知れて楽しい!」という感覚を積み重ねていくことが欠かせないのです。
パズルや迷路や間違い探しは
頭を使う良いツール
精一杯頭を使うことは、楽しいものです。人によって感覚は違いますが、往々にして簡単すぎる問題はつまらないですし、難しすぎると早々にあきらめてしまい、「楽しい」という気持ちにつながりません。
子どもによって、一生懸命頭を使えるレベルは異なります。プロであっても、それを見極めることはとても難しいものです。