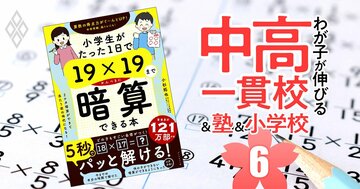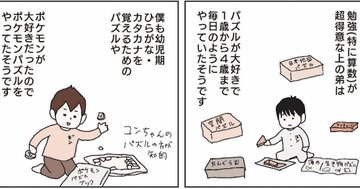一方で、「できてあたりまえ」と思われることは、つらいものです。
「みんなできているのに」や「◯年生なのにこんなことができなくてどうするの」と言われてしまうと、モチベーションは下がってしまいます。
「自分ならばできる」
幼少期から信じる力を育てる
算数はメンタルの影響を受ける教科だとお伝えした通り、問題に向き合うには自己肯定感を上げて、自信を持って解き進めることが非常に重要になります。
自信を築くためには、「結果をだせた」という経験が必要です。そして、幼少期から「自分ならばできる」と信じる力を持つことはすごく大切なことです。
自己肯定感を上げることについて、開成中学校・高校の元校長の柳沢幸雄先生のお話には大きな学びがあります。柳沢先生は、水平方向の比較、つまり他の人との比較ではなく、垂直方向の比較をしていくことが重要だといいます。
垂直方向の比較とは、「以前できなかったことができるようになった」や「精神的に成長した」など、以前の子ども自身と比較してどう変わったかという視点です。
「成績の順位が何番だったか」や「偏差値がいくつだったか」といった水平方向の比較(他の人との比較)になると、たとえ子どもが90点をとったとしても「他の子は100点をとっているんだから、もっとがんばりなさい」といった厳しい接し方になる可能性があります。
たまに、「うちの子は算数が苦手なので褒めるところがなくて」という保護者にお会いすることがあります。しかし、垂直方向の比較をすれば、絶対に褒めるところはあります。どんなに算数が苦手な子であったとしても、1年前と比べたら解ける問題が圧倒的に増えているはずなのです。
とくに幼少期のうちは、その子ができるようになったことに目を向けましょう。幼少期は、短期間でできることがどんどん増えていく時期です。できたことを1つずつ認める声がけをしていく。小さい頃からそういった経験をたくさん積んでいけると、一生ものの素晴らしい自信につながります。