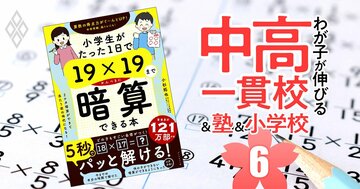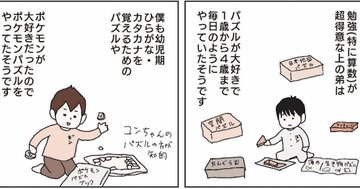教育のプロの目から見ても、「この子はこういうものを与えたら、絶対に興味を持つ」ということはわかりません。つまり、他人が予想できるものではないのです。「○○したら、△△に関心を持つ」といったコントロールはできないので、幅広くいろいろなものを経験することが大切になってきます。
そして、「子どものために何かをする」のではなく、親御さんも一緒になって楽しんでみてください。
なぜならば、「子どものために用意したのに!」という自己犠牲の気持ちが強まると、イライラしたり虚しい気持ちになったりして、子どもに八つ当たりしてしまうかもしれません。
それに繰り返しになりますが、子どもは、保護者が楽しんでいることに興味を持つことが多いものです。だからこそ、「親子で楽しめる何か」を見つけていくことがポイントになります。
子どもが学ぶ楽しさを感じる
「3つのタイミング」とは
学ぶ楽しさを味わうことは、次なる学びへ向かう原動力になります。子どもたちが学びを楽しく感じるタイミングは、大きくわけると次の3パターン。それぞれの楽しさを伝えるために、大人の接し方も異なってくるので詳しく説明していきます。
(1)成果がでる楽しさ
(2)知的好奇心が刺激される楽しさ
(3)一生懸命頭を使う楽しさ
「解けた!」「点数がとれた!」といった成功体験は、早いうちに積んだほうがいいでしょう。さらに、できたことをきちんと承認すること。
がんばってできたことに対して、評価をもらえるのは誰でもうれしいものです。とくに子どもは、親から褒められるとすごく喜びます。
成果を見えやすくすることも、子どものやる気につながるポイントです。
目標を達成したら、シールを貼ったり花丸を描いたり、子どもの達成感を喚起できるコミュニケーションを積み重ねていけるといいですね。
SAPIXに通っているご家庭でも、「計算問題に取り組んだらシールを貼って、10個集まったらお菓子を買ってあげる」というルールにしている親子がいました。ご褒美方式は賛否がわかれますが、見えやすい形で「これだけがんばれたね!」と過程を認めていく手段として活用してみてもいいかもしれません。