構造的な人手不足は
今後も長く続く
こうした推計をふまえれば、高齢化が続くことで供給が制約される一方で需要は相対的に増え、労働市場も財・サービス市場もひっ迫していくと考えることができる。
そして、財・サービス市場の需給ひっ迫は財・サービスの価格上昇につながり、労働市場の需給ひっ迫は賃金上昇につながっていく。足元で人手不足が深刻化し物価が上昇に転じている背景には高齢化に伴う需給環境の構造変化があるはずなのである。
このような状況を見て、事態の深刻さに懸念を覚える人もいるかもしれない。
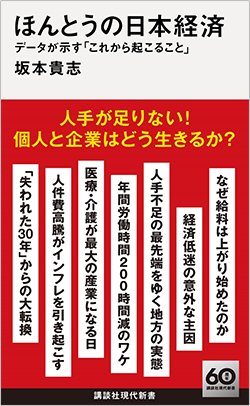 『ほんとうの日本経済 データが示す「これから起こること」』(講談社)
『ほんとうの日本経済 データが示す「これから起こること」』(講談社)坂本貴志 著
しかし、そもそもの経済活動のあり方を考えたとき、豊かな消費を行いたいという人々の欲求があって、その欲求を満たすために生産者が努力をして効率よく財やサービスを生産するというメカニズム自体は、経済学が本来想定している自然な姿である。
そう考えれば、供給に見合うだけの需要がないのだから需要を喚起せよという1990年代後半から2000年代にかけて行われた議論の方がそもそも異質だったわけで、これからの時代はサプライサイドに働きかける取り組みが重要になるという意味で、日本経済は普通の経済の姿に回帰していくことになると考えることができる。
人口減少経済に足を踏み入れているいま、日本経済の需給構造は需要不足から供給制約に様相を変えている。そして、この需給環境の変化こそがあらゆる経済構造の変化の根本にあるものなのである。
人口減少やそれに伴う高齢化の影響で、現在の人手不足は長期かつ粘着的に続く可能性が高い。そして、構造的な人手不足は、今後の日本経済に大きな変化を引き起こすことになるだろう。







