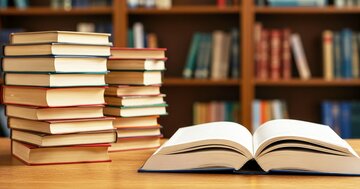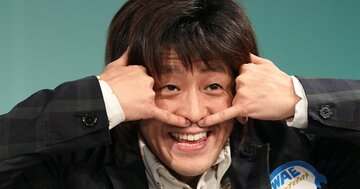そこで、反射的に口にしたのが“みんなが教師になるのを待ってるかんな”です。誰も傷つけず、適度にふざけていて面白くもあり、できそうでできないコメントです。
有田さんのような一流の人は、決して出し惜しみをしません。休憩時間に面白いことをいってもギャラも発生しないし、記録にも残らないのですが、それでも気づきを出し惜しみせず、どんどん口にするのです。
気づいたことを1人で抱えず、みんなと共有する。これは気づき力を高めていく上で重要なスタンスといえます。気づきを発信すればするほど、気づきを得やすくなる。また気づきは周りのみんなにも力を与えますし、新たな気づきを触発します。このことを脳は快く感じるので、正のスパイラルが起きるのです。だからこそ、気づいたことを出し惜しみしてはいけないのです。
SNSを見ているだけでは
「気づき」は得られない!?
今は、若者を中心に多くの人たちがSNSを情報源として利用しています。何か1つの情報を見ていると、次々と興味・関心に基づくおすすめの情報が提示されます。
一見すると効率的に情報を得て楽しんでいるようですが、冷静に考えるとAIに脳を乗っ取られ、楽しまされているともいえます。まるで、他人の夢を延々と見せられているような状態です。
私たちは延々と情報を閲覧しています。仮に何かに気づいたとしても、次々と別の情報が流れてくるので、それを見ているうちに気づきはどんどん消滅してしまいます。これを続けていくと、脳は思考停止の状態に陥っていきます。
特に深刻なのが動画です。TikTokなどを見ていると、おすすめ動画が次々と再生されます。活字の場合は止まっている文字を読み進めるので、気づきを自覚する時間的な余裕があるのですが、動画の場合はそうはいきません。
気づきが起きる前に、次の動画に目を奪われ、また次の動画に目を奪われていく……。たとえるなら、畑に芽が出た瞬間にローラーなどで踏み潰され、また芽が出た瞬間に踏み潰されるを繰り返しているようなものです。