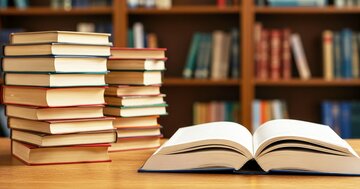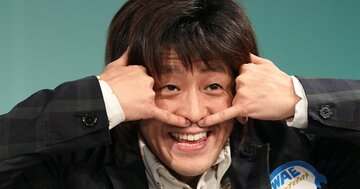写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
「気づき」の多い人が習慣にしている思考や行動とは、一体どんなものだろうか?何より大事なのは、「当事者意識」である。「もっと儲けたい」「もっとモテたい」などの強い欲求を持つことが、有効なアイデアを生み出すことに繋がるのだ。その他にも、筆者の様々な経験から「気づき」を得る方法について紹介していく。※本稿は、齋藤 孝『「気づき」の快感』(幻冬舎)の一部を抜粋・編集したものです。
日常のコミュニケーションにある
「気づき」のチャンス
ここでは、気づき力を高めるための方法について、気づきの多い人が習慣にしている思考や行動をもとに考えていきたいと思います。
社会人は、仕事の中で同僚や取引先の人たちと日々コミュニケーションを取っています。「打ち合わせの段取りを決める」という、ごく当たり前のコミュニケーションの中にも、気づきのチャンスはたくさんあります。
そもそも「打ち合わせをする」といっても、直接会う方法もあれば、オンラインでつながる方法もあります。時間や回数も、さまざまな設定が考えられます。
私たちは数ある選択肢の中から最も効率的な打ち合わせの方法を選択していきます。
「では、打ち合わせは計3回×1時間。初回は直接お会いして、2回目以降はオンラインミーティングにしましょう」
このようにアイデアを出し合いながら、お互いにとってベストな着地点を見つけ出すわけです。
効率的な方法を見つけ出せるのは、それぞれが当事者意識を持っているからです。部外者は「打ち合わせなど、勝手にやってくれ」と思うだけですが、大事な時間と労力を使う当事者は真剣です。
私の大学のある委員会では10年以上にわたり、委員全員が参加する対面の会議を行っていましたが、コロナ禍をきっかけに廃止しました。参加者は複数の校舎で仕事をしていて、1つの場所に集まるのは結構大変です。しかも、会議で行うのは主に承認です。「それなら、メールでもできるのではないか?」という提案があったので、思い切ってメール審議を試してみたのです。
高い当事者意識を持つと
「気づき」センサーが働く
結局、次年度以降もメール審議を継続することになりました。メール審議に移行しても、まったく支障がないどころか、みんなの労力が大幅に減ったからです。
メール審議も回数を重ねるうちに進化し、最近は審議用の専用フォームが登場しました。ボタンを押せば、すぐに承認できる仕組みです。参加者が「会議をもっと効率化したい」「無駄な時間を減らしたい」という当事者意識を持ったからこそ、会議の進化がもたらされたのです。