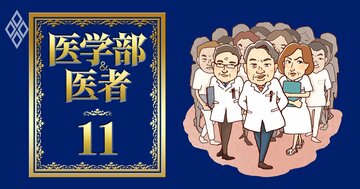治験に限らず、自分とつながりのある製薬会社にとって不都合な事実が医局から出てくるようなことがあれば、そこに圧力をかけることもできるでしょう。
実は私が東北大学の老年内科の非常勤講師を任期途中でクビになったのは、『週刊文春』に骨粗しょう症の薬の批判を書いたことがきっかけでした。当時の学会ボスから東北大学の教授宛てに電話がかかってきたようです。
これ自体は20年以上前の話ですが、薬の副作用の危険性の問題などがいまだに重要視されることがないのは、製薬会社が損をしないように学会ボスが常に目を光らせるという状況が今も続いているということなのでしょう。
このような癒着が生まれないようにも、薬の認可が降りるまでの一連の手続きは、アメリカのFDA(Food and Drug Administration:食品医薬品局/保健福祉省に属する政府機関)のような独立機関が担うべきです。
それに加えて、医局が研究費を製薬会社に依存しなくて済むような環境を整えれば、学会ボスや医局と製薬会社の癒着が生まれにくくなり、薬の過剰処方という問題の解決にも近づくのではないでしょうか。
日本の医者は薬の副作用について
積極的に知ろうとしない
原則的には保険会社が医療費を負担するアメリカでは、無駄な薬が出されるようなことは起こらず、必要最低限の種類と量しか処方されません。
保険会社だって余計なお金は出したくないので、医療機関がやみくもに薬を出そうとしても、「その薬が効くというエビデンスを出せ」とか「複数の薬を併用すると効果があるというエビデンスを出せ」などといって、簡単にそれを認めないのです。
エビデンスといっても、単に血圧が下がったというレベルのものでは認められず、例えばその薬を飲むことで5年後の脳卒中の死亡率が下がったなどという統計上のしっかりとした根拠が求められます。
また、アメリカの医者が副作用について熱心に勉強しているという背景もあります。
日本の多くの医者が副作用についてあまり真剣に考えないのは、薬の副作用によって患者さんが亡くなるようなことがあっても、医者は罪に問われないからだと私は思います。