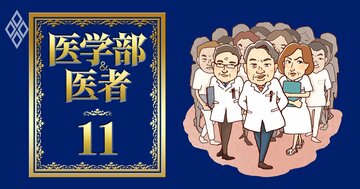写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
精神科医の和田秀樹氏によれば、研究費を得るために積極的に治験を行いたい医局は、製薬会社にとって不都合な事実を隠すのだという。それゆえに、製薬会社のMRの営業トークにおいて医者たちは薬の副作用にはほとんど興味を持たないのだ。製薬会社との癒着にまみれ、「学会ボス」が牛耳る歪んだ医療界の実態を暴く。本稿は、和田秀樹『ヤバい医者のつくられ方』(扶桑社)の一部を抜粋・編集したものです。
医局の教授たちは逆らえない
「学会ボス」とは?
喉から手が出るほど研究費が欲しい医局にとって、頼らざるを得ないのが「治験」です。
治験というのは、新しい薬を国に認可してもらうために行う臨床試験のことですが、それが実施できる医療機関は全体の10%ほどとかなり限られていて、その半数くらいは大学医学部の附属病院です。この治験が回ってくれば、依頼元の製薬会社からかなりの額の委託研究費を受け取ることができます。
つまり、治験が割り振られるかどうかは医局にとっての死活問題なのです。
実は循環器科とか、呼吸器科といった各科の治験の責任者となり、どこの大学病院に治験を割り振るかを決めるのは、多くの場合、各学会でボス的な存在となる限られた大学医学部の教授です。
このような「学会ボス」の半数くらいは東大医学部の教授が占めていて、残りの半分もそのほとんどが慶應大、京大、阪大といった、入試偏差値でいうところの難関医学部の教授たちです。
既存の学説こそが絶対正しいと言い張ったり、これまでの常識を覆すような研究データや新しい治療法を潰そうとしたりする「力のある医学部の教授たち」の多くは、まさにこの学会ボスたちのことです。
学会ボスに嫌われたりすれば、自分たちの医局に治験が回ってこなくなって資金源が途絶えてしまい、医局は危機に瀕します。だから医学部の教授たちはみな、学会ボスの言いなりとなり、内心ではおかしいと思っていても、ニセ常識に従うしかなくなってしまうのです。
そもそも単なる個人である学会のボスが治験の責任者を務めるということ自体、製薬会社と癒着してくださいといわんばかりの構図です。
製薬会社に不都合な事実は
出さないのが医局の“マナー”
報酬がどういうかたちのものかはわかりませんが、彼らのほとんどが大学教授の給料だけでは決してできないような贅沢な暮らしを送っているのは事実です。
治験を割り振られる医局にとっても製薬会社は資金源なので敵に回したくはない相手です。そういう意味でも製薬会社に有利なように治験のデータが改ざんされるようなことは絶対にないとは言い切れないと思いますが、万が一、不都合なデータを何度も出してくるような医局があったりすれば、学会ボスの判断でそこには二度と治験を回さないようにすることだって不可能ではありません。