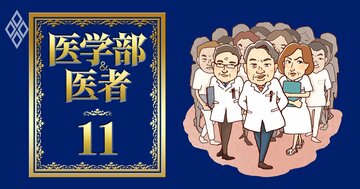訴えられるのは製薬会社だけで、医者のほうは「ガイドラインに沿って処方しただけだ」と言い逃れることができ、副作用のことを知らなかったことに対して驚くべきことに何の咎めも受けないのです。
アメリカの場合はそうはいかず、その薬の副作用のせいで患者さんの体に危険が及んだりすると、製薬会社だけでなく、処方した医者も「副作用の認識が甘かった」という理由で訴えられます。
だからアメリカの医者は薬の副作用に対する知識を蓄える努力を決して怠りません。
私がアメリカに留学していたときも、製薬会社の営業担当者(MR)から新しい薬を売り込まれると真っ先に副作用について聞く医者たちの姿をたくさん見ました。
当時の日本では通常、MRとは接待とかゴルフの話ばかりしていて、医者がMRに質問することがあるとすれば、その薬のいいところだけだったので、その違いに大きな衝撃を受けたのをよく覚えています。
副作用の知識があれば、できるだけ処方する薬の種類を少なくしようという意識が働くのは当たり前です。日本の医者が何種類もの薬を平気で処方できるのは、副作用についての知識が乏しいことの証拠でもあるのです。
学会長を務めることに
異常に執着する医学部の教授
医学部の教授たちが学会ボスに逆らえない理由は実はもう1つあります。
全国にいる医学部の教授にとって、一世一代の晴れ舞台となるのは年に1度開かれる自分の専門科での最大規模の学会(学術大会)を地元で開き、そこで会長を務めることです。
ただし、全国には82もの医学部があります。しかも50歳前後で教授になっても65歳くらいで定年を迎えますから、任期中にその夢が叶う確率は決して高くはありません。先ほど書いたような一流大学の医学部の教授のほうが選ばれやすい傾向もあるため、それ以外の医学部の教授の場合はその確率はさらに低くなります。
この貴重なポストである学会長を誰に任せるのかを決めているのが、やはり学会ボスなのです。医学部の教授たちが学会ボスの言いなりにならざるを得ないのにはそういう理由もあるのです。
なぜ、そこまでして学会長を務めたいのか。
その理由は私にもよくわかりません。