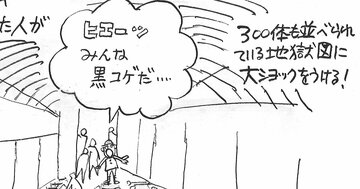文才のあった母が豪語
「小説家になっとったんよ」
母は幼い頃から読書家で、詩や物語の大好きな文学少女で、学校の教室で先生から「みんなに、創作話をして」と依頼されるほど、文才のあった人だった。
「中学しか出とらんけど、あたしには、読めん漢字はねぇ」
というのは事実その通りで、子ども時代、本を読んでいて、読めない漢字や意味のわからない言葉があると、私はいつも母に尋ねていた。
母の書いた作品を読んだわけではないものの、きっと、小説もどきのものは書いていたのではないか。
「目さえ悪うならんかったら、あたしは小説家になっとったんよ」
などと、豪語していたこともあった。
父と知り合って1年後に受けた右眼の手術が失敗して、母は後年、視力を失う。母の話は『お母ちゃんの鬼退治』(偕成社)に詳しく書いたので、ここでは省く。
父の詩のタイトル「こけし人形」とは、母のことだろう。愛しさをこめて、父は母を「こけし人形」と表現したのだろう。こけし人形の横には「、、、、、」と傍点が添えられている。ふたりだけに通じる言葉だったということなのか。
こけしの細い目と違って、母の目はぱっちりとして愛らしく、目鼻立ちもくっきりとしていて、手前味噌ではあるけれど、母は美人だった。若かりし頃の母の写真を見ると、父が一目惚れしたのもうなずける。
「あんたは、あたしには似んかった。あたしに似とれば、もっと美人になれたのに、残念じゃったなぁ」
思春期にはよく、そんな意地悪を言われて、落ち込んでいたものだった。