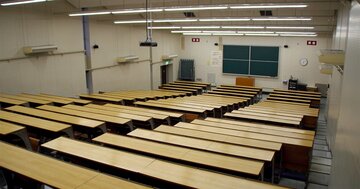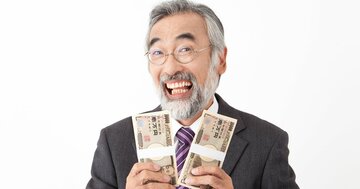写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
東大や京大をはじめとする全国の国立大学は現在、今日の国立大学は、設定された多くの数値目標で業務を徹底管理されている。かつての牧歌的雰囲気は消え去り、チェックを受ける側の膨大な事務負担ゆえに「評価疲れ」との言葉も聞かれるという。大学間、学部内、教員同士の複雑で厳格な競争の実態とは。本稿は、竹中亨『大学改革―自律するドイツ、つまずく日本』(中央公論新社)の一部を抜粋・編集したものです。
牧歌的イメージは昔の話
大学にも導入された数値目標
大学はのんびりした世界だというのが、世間の通り相場である。使い古した講義案を十年一日のごとく読みあげていれば通る世界、そう考えている人は少なくない。
しかし、大学のなかにいる人間には、そんな牧歌的雰囲気はとっくに昔語りである。今日の大学では、しばしば目標や計画が取り沙汰され、あるいは業務評価の結果が話題になる。
とくに近年、頻繁に目にするようになったのが数値目標である。正式には「重要業績評価指標」(以下、KPI)といい、業務上の目標を数値化したものである。企業では、経営企画からマーケティング、人事にいたるまで幅広く活用されている。そのKPIが大学でも導入されているのである。
すべての国立大学には、6年間の業務期間(「中期目標期間」という)の間に達成を目ざすべき「中期目標」と、達成のための具体的な取り組みを記した「中期計画」が定められている。企業でいえば中期経営計画に相当するといえようか。ウェブ上で公開されているから、簡単に見ることができる。
一瞥すれば、その細かさに驚くだろう。東京大学を見てみよう。たとえば教育の領域では、5つの中期目標と13の中期計画が掲げられている。前者は比較的抽象的な文言なので、ポイントになるのは後者である。どの中期計画も、10行近くにわたって取り組み内容をこと細かに記してある。
そして、そのどれにも必ず評価指標なるものが付いている。6年経って中期目標期間が終わったときに、その計画が達成されたかどうかを判定するための指標である。そして、この評価指標の多くはKPIなのである。
一例をあげよう。東京大学の中期計画の1つは、学際的・先端的・分野横断的な学部教育を強化することである。そこには評価指標が3つ付されていて、その1つは、学部横断型の教育プログラムの修了者数を6年後には130人にするというKPIである。
東京大学の中期計画は、教育のほか、研究、産学協同、男女共同参画、業務運営、財務など、つまり大学の業務領域全体をカバーしている。その数は全部で55個、そして評価指標は123個におよぶ。