竹中 亨
旧帝大と「その他の大学」の圧倒的な格差…大学理事が「勘弁して」と語るワケ
納税者なら誰しも、公金の使い道には関心を持つ。そうした声を反映し、国立大学に「競争」を導入すべく制定されたのが2003年の国立大学法人だ。だが、あれから20年が経ち、各大学の競争には、きしみばかりが目立つようになってきた。本稿は、竹中亨『大学改革―自律するドイツ、つまずく日本』(中央公論新社)の一部を抜粋・編集したものです。
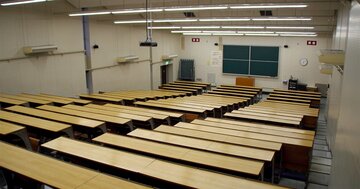
日本の大学とドイツの大学「教授人事」の決定的な違い
近年では日本の研究力の低下が盛んに指摘されているが、知の基盤を担うべき国立大学の改革は、掛け声ばかりで実を結んでいない。その原因として筆者は、大学の自己規律を軽視した教授選考制度が一端にあると指摘する。高等教育制度の構造などにおいて共通点が多いドイツと比べると、日本のとりわけ人文系学部における教授人事は、まさに「ユルユル」と呼ぶほかないのだという。本稿は、竹中亨『大学改革―自律するドイツ、つまずく日本』(中央公論新社)の一部を抜粋・編集したものです。

そりゃ「評価疲れ」にもなるわ…国立大学の複雑怪奇な評価システムにため息が止まらない
東大や京大をはじめとする全国の国立大学は現在、設定された多くの数値目標で業務を徹底管理されている。かつての牧歌的雰囲気は消え去り、チェックを受ける側の膨大な事務負担ゆえに「評価疲れ」との言葉も聞かれるという。大学間、学部内、教員同士の複雑で厳格な競争の実態とは。本稿は、竹中亨『大学改革―自律するドイツ、つまずく日本』(中央公論新社)の一部を抜粋・編集したものです。
