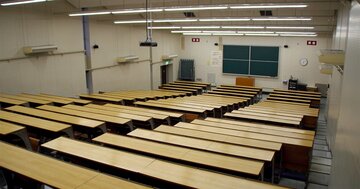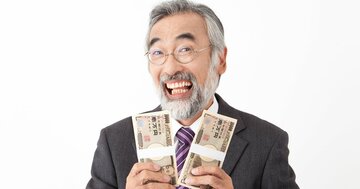この数値目標がどの程度野心的かが、審査での首尾をわける大きな材料となる。と同時に、採択されれば、計画進捗のチェックを受ける際の指標ともなるのである。
定期的に行われる複雑な法人評価
審査は大学の全ての業務におよぶ
目標を掲げる以上、それを実際に達成したか否かは当然チェックの対象となる。こうして全国立大学を対象に、中期目標期間の中間と期末の2回、いわゆる「法人評価」(正式には、「国立大学法人評価」)が一斉に行われる。
法人評価の目的は、中期目標・中期計画の達否を審査することである。中期目標・中期計画の広範さに照応して、法人評価の対象範囲もまた教育・研究をはじめ、大学のすべての業務におよぶ。審査では、1つ1つの目標・計画について、内容に即してその達成度を見る。
これを「達成状況評価」という。
注意したいのは、中期計画は大学ごとに異なるから、大学の評価はあくまでもその大学の掲げる目標・計画の達成具合で決まる点である。乱暴なたとえだが、「鉄棒の逆上がり」を目ざす児童Aと、「縦笛を吹ける」を目標とする児童Bの成績をつけるのと似ている。
問われるのは、それぞれが鉄棒と縦笛でどこまで上達したかである。逆にいえば、Aがどんな点数をとろうと、Bの点数には影響しない。
ただ、やっかいなことに、法人評価の仕組みはこれだけではない。達成状況評価以外に「現況分析」というものがある。これは事実上、当該の大学の教育・研究がどのくらいの水準にあるかを評価するものである。
さて問題は、何をもって水準の高い低いを判断するかである。考えられるのは唯一、国立大学ならこの程度が平均的、というような目算であろう。だとすれば、現況分析の評価は、暗黙裡に他大学との比較を前提にしているわけである。
法人評価としての判定は、達成状況評価に現況分析を加味して下される。評価結果は次期の予算に反映される。運営費交付金の中に設けられた「法人運営活性化支援」という枠が、法人評価での成績に応じて算定されるのである。
以上でわかるように、法人評価の仕組みはかなり複雑、むしろ面妖といっていい。その大学だけを見る個別評価に、他大学を視野に入れた比較評価をかけ合わせる仕組みだからである。
先のたとえを続けるなら、鉄棒と縦笛でのA、Bそれぞれの点数に、他の児童も交えて行った算数のテストでの各自の点数を混ぜこむようなものである。