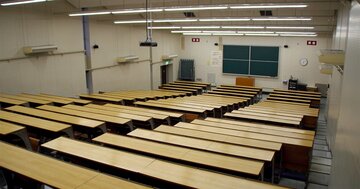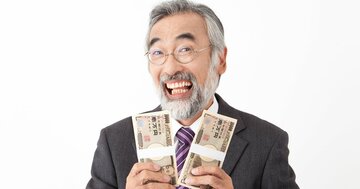大学活性化の仕組みが
「評価疲れ」になる皮肉
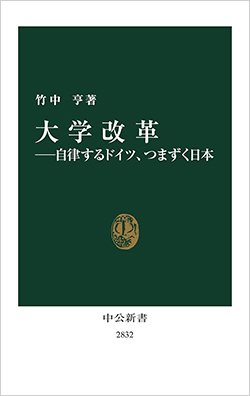 『大学改革―自律するドイツ、つまずく日本』(中央公論新社)
『大学改革―自律するドイツ、つまずく日本』(中央公論新社)竹中 亨 著
いずれにしても、この2本立ての評価作業が大学それぞれについて行われる。国立大学法人は現在82あり、その下に86の国立大学がある(1法人中に複数大学が存在する場合があるため)。これに「人間文化研究機構」など4研究機関が加わる。これだけの数の機関について、法人評価ではその業務を総ざらいするのである。いかに大事業かは察しがつこう。
だから、評価体制は大がかりである。いわゆるピア・レビュー方式をとっており、評価者を務める教員・研究者が全国の大学や研究機関から動員されるが、その数は1000人に近いという規模になる。金子元久(編集部注/東大名誉教授。高等教育研究の第一人者とされる)の述べるごとく、「世界でもっとも包括的で、おそらくもっとも野心的な」(Kaneko 2009:65)(注1)大学評価なのである。
評価するほうも大がかりだが、評価される大学側の事務負担も膨大である。まず、中期目標・中期計画の達成状況を1つ1つ調査し、そのうえで状況を仔細に示す大部の自己評価書を作成しなければならない。
現況分析のためには、学部ごとに教育・研究の全般的状況を示す報告書も必要である。また研究については、個々のプロジェクトの中味に立ち入った詳細な報告書を作成する。さらに加えて、これら報告書のエビデンスとなる関連資料を学内各所からそろえなければならない。
以上の準備作業と審査本番を合わせると、法人評価を受けるには1年以上かかる。法人評価は6年間の中期目標期間に2回あるから、つまり6年のうち半分近くは評価に関わっている計算である。
今日の大学関係者の間では「評価疲れ」という語が広まっている。たしかに、これほど次から次へと評価に追いまわされていたら(しかも、実際にはさらにまだ別の評価がある)、疲れるのも無理はない。
大学を活性化するはずのコントロールの仕組みが、かえって教育・研究にエネルギーをふり向けるのを阻んでいるとしたら、皮肉である。