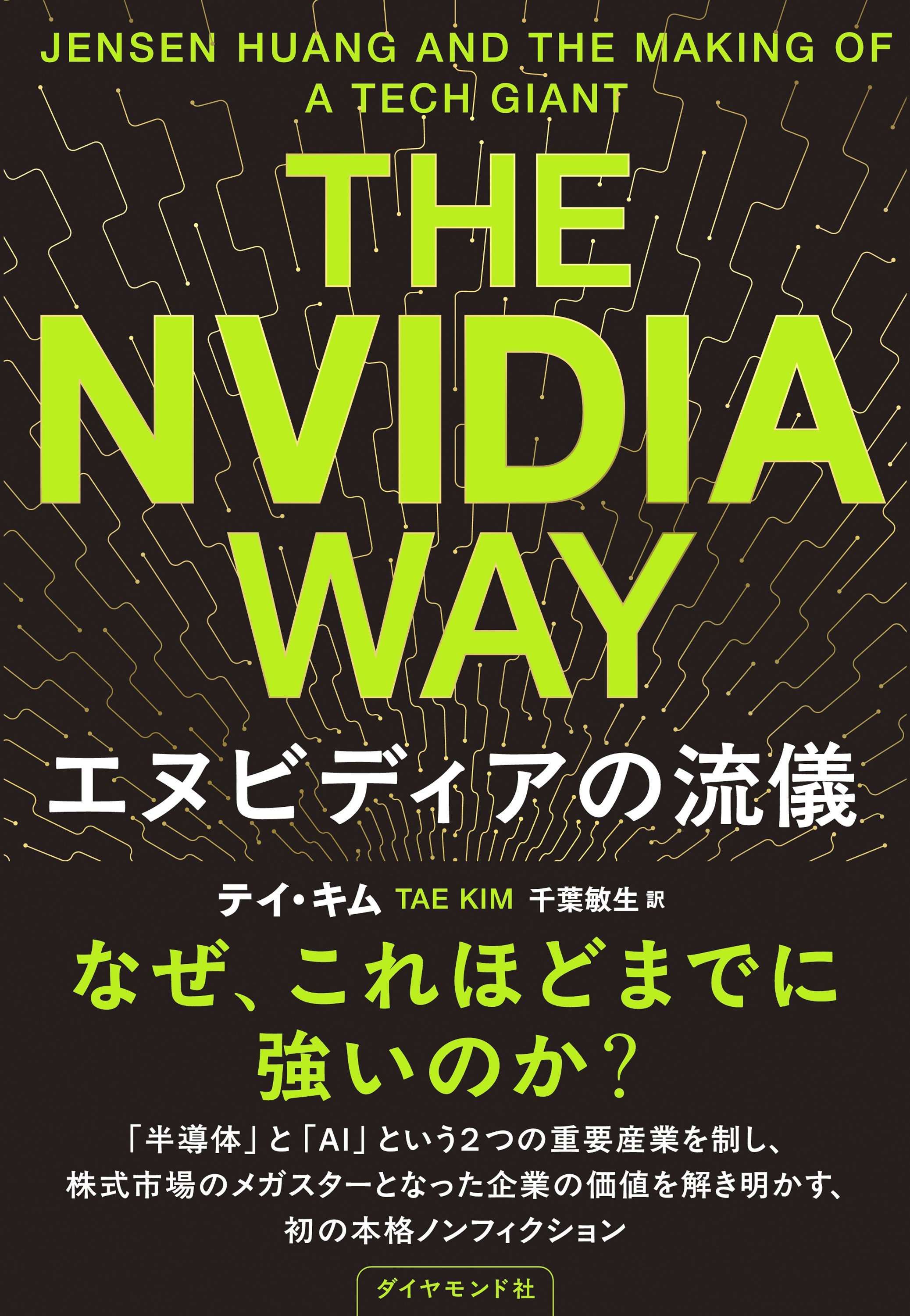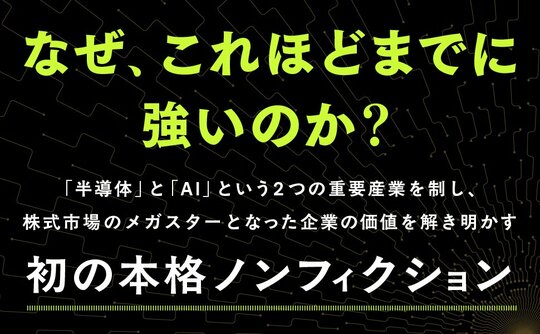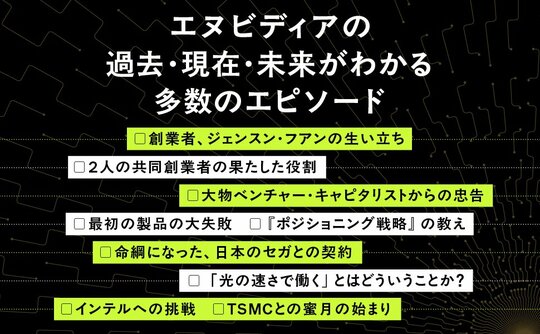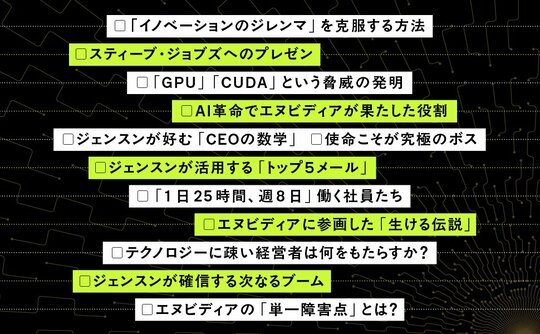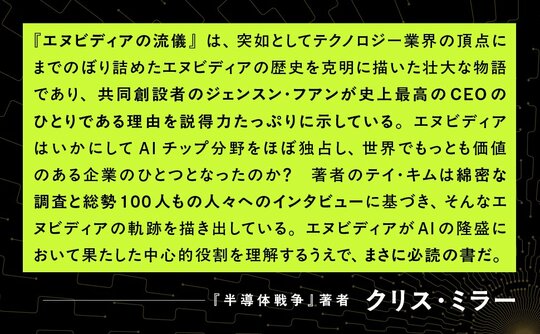アップル、マイクロソフトと世界の時価総額ランキング1位を争い、誰もが知る企業となったエヌビディア。「半導体」と「AI」という2つの重要産業を制し、誇張ではなく、米国の株式市場、そして世界経済の命運を握る存在となった。しかし、その製品とビジネスの複雑さから、エヌビディアが「なぜ、これほどまでに強いのか?」ついては真に理解されているとは言えない状況だ。『The Nvidia way エヌビディアの流儀』は、その疑問に正面から答える、エヌビディアについての初の本格ノンフィクションである。
今回は同書より、起業を思い立ったカーティス・プリエムとクリス・マラコウスキー(当時サン・マイクロシステムズに勤務)が、ジェンスン・フアン(当時LSIに勤務)を創業メンバーに引き入れた際のエピソードを紹介する。
 Photo: wolterke/Adobe Stock
Photo: wolterke/Adobe Stock
ジェンスン・フアンが、一番起業に慎重だった
1992年終盤、プリエム、マラコウスキー、ジェンスンは、イースト・サンノゼのキャピトル通りとベリエッサ通りの交差点に面するデニーズで頻繁に打ち合わせを重ね、自分たちのアイデアをビジネス・プランに変える方法を話し合った。
「入店したらまず、お代わり自由のコーヒーを1杯注文する。そのあと、4時間くらいみっちり仕事をしていたよ」とマラコウスキーは言った。
プリエムは、デニーズのパイやグランドスラム・ブレックファスト(2枚のバターミルク・パンケーキに、目玉焼き、ベーコン、ソーセージを添えた朝食メニュー)を飽きるほど食べたのを覚えている。ジェンスンは自分の定番の注文を覚えていないが、たぶんスーパーバード・サンドイッチだったと思っている。七面鳥の肉、とろけるスイス・チーズ、トマトに、彼のお気に入りであるベーコンをトッピングしたサンドイッチだ。
それでも、ジェンスンはすんなりと仕事を辞める気にはなれなかった。辞めるにはそれなりの確信が必要だった。食事の合間に、彼はカーティスとクリスを質問攻めにし、ビジネス・チャンスの規模についてたずねた。
「そのPC市場ってのはどれくらい巨大なんだ?」とジェンスンは訊いた。
「そりゃあ巨大さ」とふたりは答えた。それは事実だったが、どう見てもジェンスンを満足させられるほど詳しい説明とはいえなかった。
「クリスと私はひたすらジェンスンを見つめたまま座っていたね」とプリエムは言う。ジェンスンはPC市場や潜在的な競合相手について分析を続けていた。ふたりのスタートアップ企業には成功の可能性がある、と彼は思ったが、ビジネスモデルに納得がいくまでは今の仕事を辞めたくなかった。クリスとカーティスが自分の存在を不可欠だと考えてくれたことはありがたかったが、彼は内心こう思ったのを覚えている。「私は自分の仕事が大好きだが、君たちは自分の仕事に嫌気が差している。私はうまくやっているが、君たちは行き詰まっている。なんの義理で私が君たちと一緒に仕事を辞めなきゃならないんだ?」
そこでジェンスンは、そのスタートアップ企業が最終的に年商5000万ドルを達成できると証明してくれたら加わってもいい、と告げた。
ジェンスンはデニーズでの長い会話を懐かしく振り返る。「クリスとカーティスは僕が今まで会ったなかでいちばん頭の切れるエンジニアで、コンピュータ科学者だった」と彼は言う。「成功には運がつきものだけれど、私にとっての幸運はふたりに出会えたことだね」
誰が最初に会社を辞める?
結局、ジェンスンは年商5000万ドルの達成は可能だと判断した。ひとりのゲーマーとして、ゲーム市場が大きく成長するという確信があったのだ。
「私たちはビデオゲーム世代の人間だ」と彼は言う。「ビデオゲームやコンピュータ・ゲームの持つ娯楽的な価値は、私にとっては明白だったんだ」
となると次なる疑問は、誰が最初に動くかだった。プリエムは先陣を切る覚悟ができていた。サンで置かれた状況を考えれば、どのみち数か月後に会社を辞めるはめになるのは目に見えていた。ところが、ジェンスンの妻ロリは、マラコウスキーがサンを去るまでは夫にLSIを辞めてほしくなかった。一方、マラコウスキーの妻メロディは、ジェンスンの約束が得られるまで夫にサンを辞めてほしくなかった。
1992年12月、プリエムがふたりの背中を押す行動に出る。12月31日付でサン・マイクロシステムズへの辞表を提出したのだ。そしてその翌日、自宅でひとり、新規事業を立ち上げた。「といっても、新規事業を始める、と宣言しただけだけどね」と彼はのちに振り返っている。
それさえも少し言いすぎだった。まだ社名も資本金もなければ、従業員もいない。マラコウスキーやジェンスンもまだ仲間に加わっていなかった。彼にあったのはたったひとつのアイデアと、友人たちに対する一定の影響力だけだった。
「このカーティスをひとりで苦しませるなんて許さない、とふたりに圧をかけたんだ」とプリエムは語る。それどころか、ふたりに半ば罪悪感を植えつけたという。「カーティスが辞めたからには自分も辞めないと、と言ってふたりも加わった。ふたりは同時に辞めたから、妻との問題も一件落着した。こうして、僕らはひとつのチームになったんだ」
マラコウスキーは、彼の最後のプロジェクト、GXシリーズのアップグレードを見届けるまで、サン・マイクロシステムズに残ることにした。部下のエンジニアたちがチップの完成を確認すると、彼はようやく安心し、1993年3月上旬をもって会社を去ると宣言した。
「優秀なエンジニアは職務を放り出して辞めたりはしないものさ」とマラコウスキーは言った。
そして、優秀なエンジニアは商売道具を放り出して辞めたりもしない。退社の前、マラコウスキーは新たなスタートアップ企業に自身のサンのワークステーションを持っていきたい、と申し出た。まだ彼の上司だったウェイン・ロージングが持っていくことを認めると、マラコウスキーは退社前の数日間で自身のワークステーションのなるべく多くの部品をアップグレードした。
「メモリ、ディスク・ドライブ、モニター・サイズを最大限までアップグレードしたよ」とプリエムは言った。
ジェンスンもまた、LSIを円満に退社したいと思っていた。彼は1993年の最初の6週間をかけて、自身の担当プロジェクトをほかのリーダーたちに割り振っていった。彼が正式にプリエムのチームに加わったのは2月17日。くしくもジェンスンの30歳の誕生日だった。