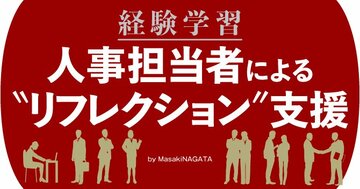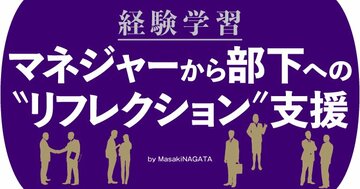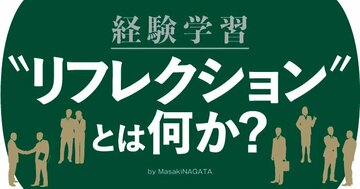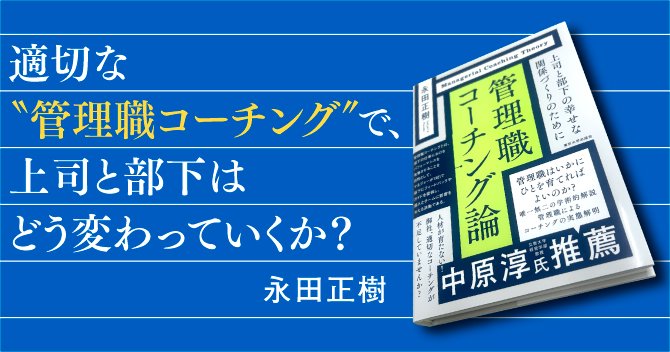
コロナ禍を経てのリモートワークの一般化、さまざまなハラスメントが生じるリスク――管理職やマネジャー、上司が、部下を育成しづらい時代になっている。一方で、人的資本経営が重視され、人を育て、就労者のワークエンゲージメントを上げ、離職率を下げていくことが組織に課せられた重要なミッションになっている。どうすれば、上司と部下の幸せな関係がつくれるのか? “教え上手なマネジャー”たちへのインタビューを実践し、定性&定量データから導き出した「管理職コーチング」の手法とは? 書籍『管理職コーチング論 上司と部下の幸せな関係づくりのために』の著者である永田正樹さんが説いていく。(ダイヤモンド社 人材開発編集部)
人的資本経営で“管理職コーチング”が必要な理由
上司と部下の幸せな関係づくりは可能なのか、可能だとしたら、上司はどのような行動を取ればよいのだろうか――私のそんな問いは、東福寺の縁側から生まれた。東福寺は、京都市東山区にある臨済宗の寺である。その日は、午前中に京都の企業の人事担当者と打ち合わせがあった。午後からは予定がなかったので、東京の勤務先に帰社するのが通常である。しかし、私は東福寺を訪れ、東福寺の縁側に座り、頭を空っぽにしようと努力しつつ、午後いっぱいの時間を費やした。別に仕事をサボりたかったわけではない。当時、私は部下との関係がうまくいかずに悩んでいた。会社にいると、誰かが私のことを批判しているような気がして、まさに針の筵(むしろ)のような気分だった。初夏、静謐な空気の流れる古寺の縁側で、部下との関係づくりについて考える中で、前述の「上司と部下の幸せな関係づくりは可能なのか、可能だとしたら、上司はどのような行動を取ればよいのだろうか」という問いが生まれた。
その頃の私は、部下からの質問やチーム内で起こる出来事の全てに自分で答えを出そうとしていたように思う。また、部下が担当する仕事の多くに顔を突っ込み、私の指示のもとで仕事をやらせようとしていた。それがマネジャーの役割だと思っていたからだ。つまり、部下の手を借りずに、手っ取り早く、自分でやってしまい、業績を上げようとしていたのだ。そうなると、部下は自律的に仕事をすることができず、本来味わえるはずの仕事を達成した時の有能感や楽しさを味わえない。そして、それを奪う上司を疎ましく思うようになる。こうして、上司と部下の不幸せな関係が始まるのである。
職場における上司と部下の関係は企業経営にも影響を及ぼす。離職やリテンションの問題に最も強い影響を与えるのは上司と部下の関係が大きい。人口減少社会の中で、優秀な従業員を確保・育成し、会社に引き留めるためには、上司と部下の関係、職場の健全性が大きな影響を及ぼす。そして、「上司と部下の幸せな関係づくり」のために注目を浴びているのが、「管理職コーチング」であり、人的資本経営の時代に注目される指標であるエンゲージメントも「管理職コーチング」によって向上するという多くの報告がある。