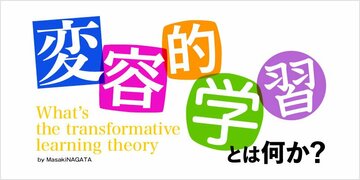永田正樹
「なぜか部下に好かれる上司」が言っている、“たった4文字”の魔法の言葉とは?
あなたの部下はこの1年、どんな仕事をしていましたか? 最後に一対一で話をしたのはいつでしょうか? 上長と部下が一対一で行う「1on1ミーティング」は今や多くの職場で“当たり前”となりました。ヤフーが実践してきたこの対話手法は、単なる業務報告や評価面談とは異なり、部下の成長を支援し、信頼関係を築くためのものです。

「なぜか若手社員が育たない職場」で上司が勘違いしていること、ワースト3
あなたの部下はこの1年、どんな仕事をしていましたか? 最後に一対一で話をしたのはいつでしょうか? 上長と部下が一対一で行う「1on1ミーティング」は今や多くの職場で“当たり前”となりました。ヤフーが実践してきたこの対話手法は、単なる業務報告や評価面談とは異なり、部下の成長を支援し、信頼関係を築くためのものです。

「部下が育てられない管理職」がよく言うNGワード2選。「次は頑張ろう」、あともう一つは?
あなたの部下はこの1年、どんな仕事をしていましたか? 最後に一対一で話をしたのはいつでしょうか? 上長と部下が一対一で行う「1on1ミーティング」は今や多くの職場で“当たり前”となりました。ヤフーが実践してきたこの対話手法は、単なる業務報告や評価面談とは異なり、部下の成長を支援し、信頼関係を築くためのものです。

「この人の下で働きたい」と部下が思う上司だけが知っている、部下の勘所とは?
あなたの部下はこの1年、どんな仕事をしていましたか? 最後に一対一で話をしたのはいつでしょうか? 上長と部下が一対一で行う「1on1ミーティング」は今や多くの職場で“当たり前”となりました。ヤフーが実践してきたこの対話手法は、単なる業務報告や評価面談とは異なり、部下の成長を支援し、信頼関係を築くためのものです。

「この人なら話せる」部下にそう思わせる「なぜか好かれる上司」がやっている、たった一つのこと
あなたの部下はこの1年、どんな仕事をしていましたか? 最後に一対一で話をしたのはいつでしょうか? 上長と部下が一対一で行う「1on1ミーティング」は今や多くの職場で“当たり前”となりました。ヤフーが実践してきたこの対話手法は、単なる業務報告や評価面談とは異なり、部下の成長を支援し、信頼関係を築くためのものです。

適切な“管理職コーチング”で、上司と部下はどう変わっていくか?
コロナ禍を経てのリモートワークの一般化、さまざまなハラスメントが生じるリスク――管理職やマネジャー、上司が、部下を育成しづらい時代になっている。一方で、人的資本経営が重視され、人を育て、就労者のワークエンゲージメントを上げ、離職率を下げていくことが組織に課せられた重要なミッションになっている。どうすれば、上司と部下の幸せな関係がつくれるのか? “教え上手なマネジャー”たちへのインタビューを実践し、定性&定量データから導き出した「管理職コーチング」の手法とは? 書籍『管理職コーチング論 上司と部下の幸せな関係づくりのために』の著者である永田正樹さんが説いていく。
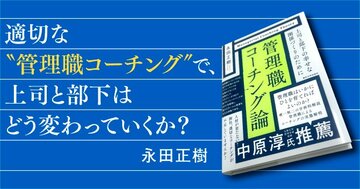
新入社員を成長させる、日本光電の“エルダー制度”と“経験学習”の仕組み
医療機器の開発・製造・販売を行う日本光電工業株式会社は、1951年の創業以来、「エレクトロニクスで病魔に挑戦」をモットーに、さまざまな医療機器を世界各地の医療現場に提供している。人に寄り添った“モノづくり”を行う同社は、従業員一人ひとりの力を最大限に引き出すことを念頭に、「人材」を「人財」とし、その育成に力を注いでいる。新人1人に対し、1名の育成指導担当者がつく「エルダー制度」はどのようなものか? 人財育成の根幹をなす経験学習のサイクルをどう回しているのか? 同社グローバル経営管理本部フェニックス・アカデミー副所長の茂木順子さんと人財開発本部フェニックス・アカデミー研修チームリーダーの髙木綾香さんに話を聞いた。

若手・中堅・シニアの“ジョブ・クラフティング”を、企業はどう支援すればよいか
人的資本経営の推進が求められるなか、多くの企業でエンゲージメントの向上が重要課題となっている。その解決手段として、従業員が働きがいを自ら高める“ジョブ・クラフティング”への注目度が高まっている。ジョブ・クラフティングとは何か、企業はジョブ・クラフティングをどのように支援するべきか――2024年6月刊行の書籍『50代からの幸せな働き方 働きがいを自ら高める「ジョブ・クラフティング」という技法』の著者であり、ジョブ・クラフティング研究で著名な高尾義明さん(東京都立大学大学院経営学研究科 教授)に話を聞いた。

経験学習において、人事担当者が行える“リフレクション”支援を考える
人材育成の手法のひとつとして知られる「経験学習」で、ことさら重要なのが「内省的観察」のステップだろう。“リフレクション”と呼ばれるこの行動は、研究者によって多くのとらえ方(解釈)があり、正しい実践はなかなか難しいようだ。効果的な“リフレクション”を実現するために、マネジャーは部下をどう支援すべきか――それを説いた前回記事に続き、今回は人事担当者が行える“リフレクション”支援を考える。
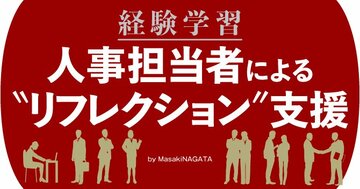
ダイバーシティを実現する、ハウス食品グループの“組織風土改革”とは?
ハウス食品グループはカレーやシチューの素などの商品がおなじみだが、国内外に43の連結子会社を持ち、グローバルに価値を創造する企業グループへの変革に取り組んでいる。従業員の「属性」「経験」「適性」も多種多様になっており、成長を実現するために多様な個性の発揮と融合を促進している。「全員参加の職場の改革サイクル」と「会社の風土改革サイクル」を回して目指すものは、「一人ひとりが働きがい(成長実感・チャレンジ)を感じながら変革に向けて挑戦する組織」だという。ハウス食品グループ本社株式会社・人材戦略部の根耒伸至さん(人材・組織開発課長)と井ノ上友美さん(学習機会開発課 学習機会開発チーム チームマネージャー)に話を聞いた。

Hondaの人材育成施策に見る、「エンゲージメント」を高めるキャリア支援
「私はいつも、会社のためにばかり働くな、ということを言っている。自分のために働くことが絶対条件だ」――これは、本田宗一郎氏(本田技研工業創業者)が1969年(昭和44年)に同社の従業員に向けて発信した言葉だ。激動の自動車業界のなか、「人や社会の役に立ちたい」「人々の生活の可能性を拡げたい」という想いを原点にするHonda(本田技研工業株式会社)は、人事関連領域でも変革と挑戦を続けている。従来の「階層別研修」から「新たな研修体系」への転換など、新たな人材育成施策と現況を人事部のキーパーソンたちに尋ねた。

経験学習での、マネジャーから部下への“リフレクション”支援を考える
人材育成の手法のひとつとして知られる「経験学習」において、重要なのが「内省的観察」のステップだ。“リフレクション”と呼ばれるこの行動は、研究者によって多くのとらえ方(解釈)があり、正しい実践がなかなか難しい。組織における効果的な“リフレクション”を実現するために、マネジャーは部下をどう支援すべきか――人事担当者向けのセミナーなどに多数登壇している永田正樹さんが解説する。
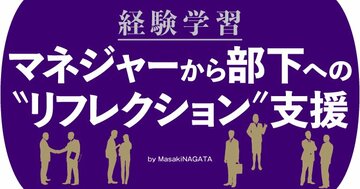
LINEの「HRBP(HRビジネスパートナー)」が事業成長のために行っていること
人・情報・サービスをつなぐコミュニケーションアプリ「LINE」。日本国内の月間アクティブユーザー数は約9500万人におよび、生活を支えるプラットフォームとして欠かせない存在になっている。そして、そのアプリを運営・開発するLINE株式会社においては、サービスの継続&成長を人事・組織面から戦略的に支える「HRBP(HRビジネスパートナー)」が欠かせない存在になっている。HRの水先案内人となる「HRBP」の役割とは? 各事業部のマネージャーに伴走する方法とは? HRBPチームをマネジメントする、LINE株式会社HR Business Partner室の大野道子さんと小向洋誌さんに話を聞いた。

経験学習における“リフレクション”は、どうすれば効果的に行えるか?
人材育成の手法のひとつである「経験学習」において、「具体的経験」に続くステップが「内省的観察」だ。「リフレクション」と呼ばれる、その行動は、研究者によって多くの捉え方があり、実践することがなかなか難しい。日々働く中で、効果的なリフレクションを実現するために、個人はいったいどうすればよいのか? 人事担当者向けのセミナーなどに多数登壇している永田正樹さんが、経験学習における“リフレクション”について解説する。
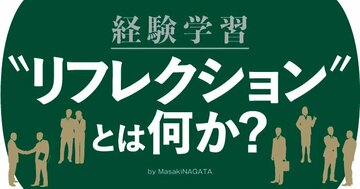
良質な“仕事経験”を得ていくために、本人とマネジャーと人事部門に必要なこと
企業における人材の成長は「仕事上の直接経験」によるものが多いと言われている。人材育成の手法のひとつである「経験学習」の最初のステップでもある「具体的経験」――では、仕事での良い「経験」とはどのようなもので、どうすれば、個々人が獲得できるのだろうか? 「経験学習」についての研修など、人事担当者向けのセミナーに多数登壇している筆者が、“人材を成長させる経験”について解説する。
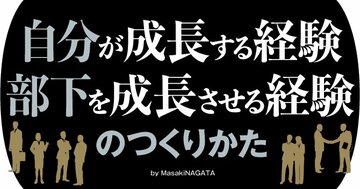
三井住友海上インタビュー(2)人事部の私たちも、失敗を恐れずにチャレンジすることが大切
学生の就職希望先としても人気の高い三井住友海上火災保険株式会社(MS&ADインシュアランス グループ)。本年度(2022年度)からスタートした中期経営計画では、「人財」を、会社の基本方針・重点施策を支えるための「経営基盤」と位置づけ、その採用と育成によりいっそう注力している。自己啓発支援としての「エンパワーメントセミナー」「学人(まなびと)サークル」、職場での人財育成支援としての「ファミリー制度」など、同社ならではの試みからは他社が学べることも多いだろう。人事部の丸山剛弘さんと丸山紀子さんに話を聞いた。

三井住友海上インタビュー(1)一歩踏み出してチャレンジできる“人財”こそが、競争力の源泉
学生の就職希望先としても人気の高い三井住友海上火災保険株式会社(MS&ADインシュアランス グループ)。本年度(2022年度)からスタートした中期経営計画では、「人財」を、会社の基本方針・重点施策を支えるための「経営基盤」と位置づけ、その採用と育成によりいっそう注力している。自己啓発支援としての「エンパワーメントセミナー」「学人(まなびと)サークル」、職場での人財育成支援としての「ファミリー制度」など、同社ならではの試みからは他社が学べることも多いだろう。人事部の丸山剛弘さんと丸山紀子さんに話を聞いた。

JTBは、さまざまな研修を社員の“行動変容”にどうつなげているのか
オンラインでのサービスはもちろんのこと、国内で300店舗以上の窓口を持ち、さまざまな「旅行体験」をそれぞれの消費者に提供している、国内ツーリズム産業最大手の株式会社JTB。「地球を舞台に、人々の交流を創造し、平和で心豊かな社会の実現に貢献する。」を経営理念とし、その数多(あまた)の事業を支えているのは、社員一人ひとりが持つ「人間の力」だという。グループ従業員約2万名にも及ぶ人材の育成はどのようになされているのか? グループ本社 人財開発チーム 人財開発担当部長 中村彰秀さんに話を聞いた。

「経験学習」とは何か?新入社員が“仕事上の直接経験”で成長する方法
4月入社の新入社員が、それぞれの組織に配属されていく季節だ。人事部の手を離れ、各部門に飛び立った彼ら彼女たちをしっかり成長させていくために、人材育成の手法のひとつである「経験学習」を回していく組織も多いだろう。そこで改めて、「経験学習とは何か? 新人をはじめとしたビジネスパーソンが、経験学習を身につけるために教育担当者や管理職はどうするべきか?」を考えてみる。

「優秀さの罠」から抜け出したマネジャーが、組織の中で見つけたもの
自分の視点や考え方を変えることはなかなか難しい。特に、幼少期に無自覚に獲得した物事の見方や感じ方・行為のあり方は、知らず知らずのうちに仕事にも影響を与えていく。多様な人材が一堂に会する時代――偏った経験による価値観を変容させながら“個と集団の成長”を促すためには、誰がどうすればよいのか? 米国の社会学者ジャック・メジローが提唱した「変容的学習論」をもとに考えてみよう。