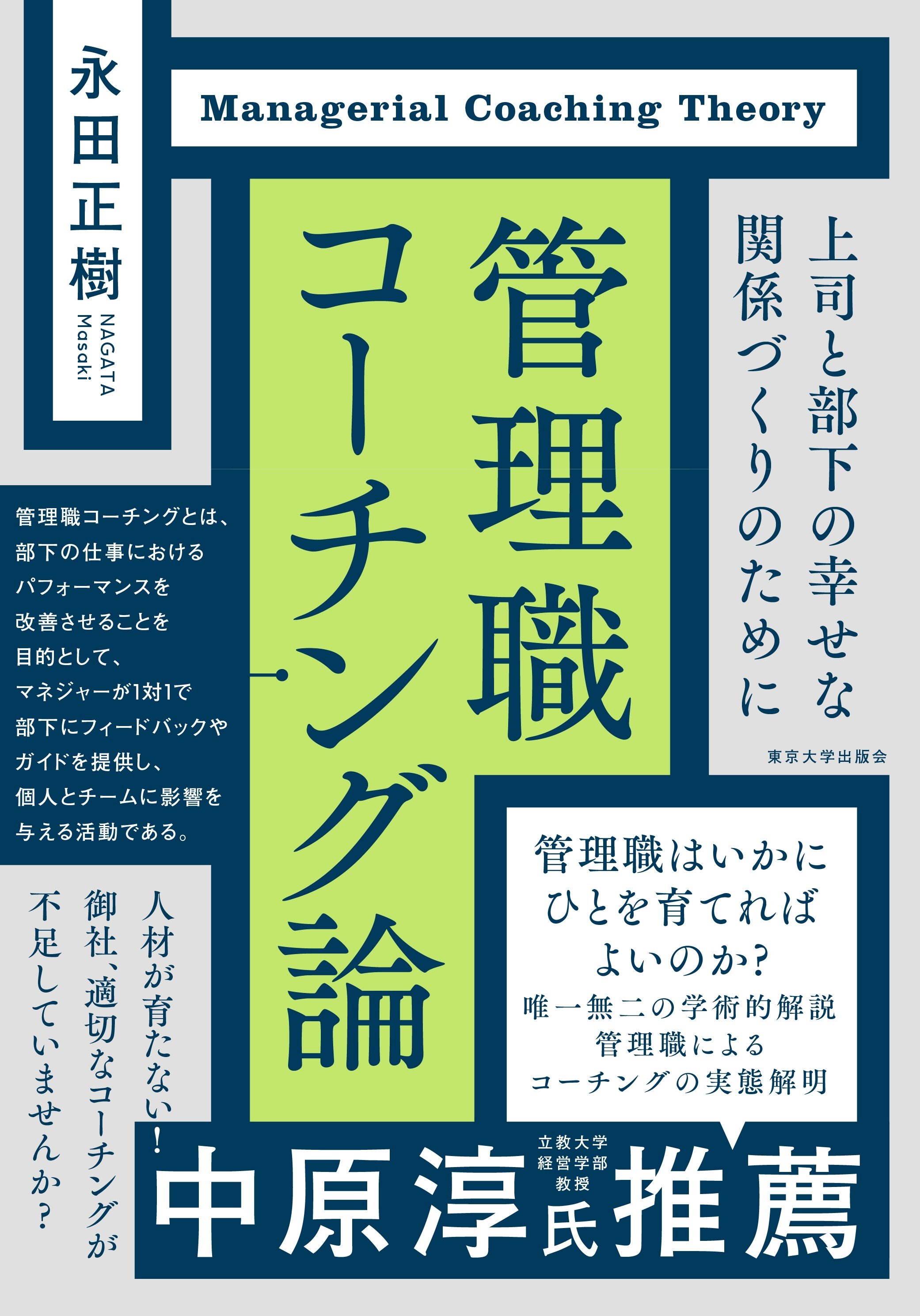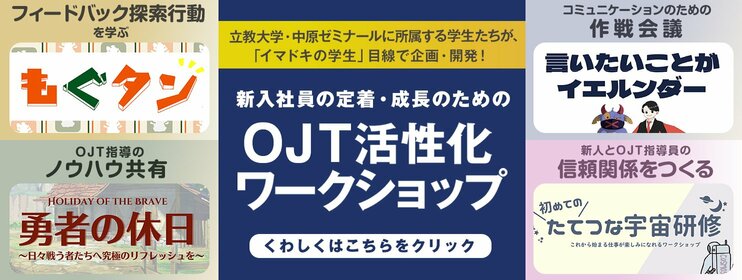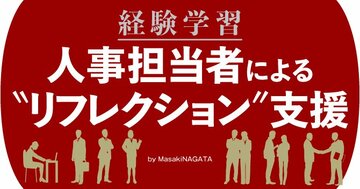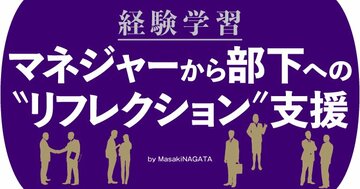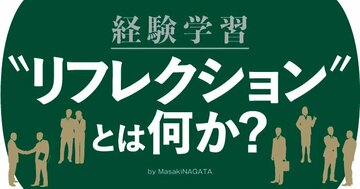上司と部下の幸せな関係づくりのためには…
まずは、「成長支援の準備」である。具体的な育成行動として、「部下同士が、お互いに知り合うための場づくりをしている」「失敗を許容する環境づくりを心がけている」「自分のことをオープンに話し、自己開示している」などが該当する。一言で言うと、心理的安心感を醸成することであろう。このような環境の中で、部下は本音を話し、自由に意見を言うことができる。同僚からも安心してフィードバックを受けることが可能となり、結果としてリフレクションが促され、学習が生まれる。育成上手のマネジャーのコメントとしては、以下のような行動が該当する。
「チーム内の関係の質を上げるためには、お互いのことをよく知る必要がある。そのため、月に2回のランチで、過去の生い立ち、入ってからやった仕事、仕事の中でやり遂げたいことを話し合っています。チームメンバー間でも、案外、お互いのことを知らないものです」
次に、アサインメントをする際の、仕事の意味づけである。具体的な育成行動としては、「仕事の背景や目的を明確に伝えている」「部下のなりたい姿と仕事の関わりを示している」などが該当する。部下が仕事の意味を感じることは、パフォーマンスにつながることはもちろん、離職防止にもつながる。部下がどのようなことに意味を感じるのかを個別に把握したうえで、仕事を意味づける必要がある。仕事に意味が感じられれば、部下は挑戦的な課題にも前向きに立ち向かう。このような良質な経験が、部下の成長を促すと思われる。育成上手のマネジャーのコメントとしては、以下のような行動が該当する。
「ほとんどの部下が自分の強みを発見できません。強みを発見するコツは美点凝視だと思います。輝いている自分を思い出させたり、職場で全員の良いところを書かせて、それを交換することにより、他者から自分の強みを指摘してもらったりします。『好きな分野』『得意な分野』『人のためになる分野』の重なり合うところがその人の強みです。弱みは変えられないので、強みを伸ばした方が良いと思う。そのうえで、いまの仕事の中で、強みがどこで使えるかを見極めさせ、組織の中の自分の役割を発見させます」
最後に、リフレクション支援である。具体的な育成行動としては、「部下に答えを与えず、ヒントを与えて本人に考えさせ、仕事をやり切らせている」「仕事のゴールは伝えるが、プロセスは部下に考えさせるようにしている」が該当する。つまり、部下に考えさせるような関わり方が必要ということであろう。上司から指示され、上司が敷いた線路の上を走り、ゴールを達成しても、部下の学びは少ない。それよりも、ゴールは明確に示すものの、仕事の進め方は部下に任せ、試行錯誤しながらもゴールにたどりついた方が、部下の学びは大きい。自分で経験し、つかんだ答えは一生忘れない。本人が仕事を進める上での宝になるのであろう。育成上手のマネジャーのコメントとしては、以下のような行動が該当する。
「何を期待しているかを伝え、ゴール感は伝えるが、プロセスは自分で考えさせます。山の登り方はいくつもあるので、同じ山を登るのでも、本人がどういったルートを取りたいのかを決めさせます。決められなかったらサジェスチョンする。プチ成功体験を積めるほど、本人は主体的に動き出します」
私が著した『管理職コーチング論 上司と部下の幸せな関係づくりのために』では、「上司と部下が幸せな関係づくり」をするための型を示した。もちろん、数多(あまた)ある上司と部下の関係に、本書で示した型が全て適用できるものではない。しかし、18代中村勘三郎は「型を知っていれば、それを崩しても型破りになる。型を知らなければ型なしになる」と言っている。心の余裕をなくし、部下育成に悩むビジネスパーソンの方々に、本書が羅針盤として、何らかの貢献ができたら幸いである。現在も私は、「歩き屋」(フィールドワーカー)として、さまざまな企業の育成上手のマネジャーへのインタビューを続け、また、企業の管理職研修で、私が研究で得た「型」を広める活動をしている。「上司と部下の幸せな関係」が一つでも多く生まれることを祈って。