扉の向こうへ
日本流の開祖の一人である西田幾多郎は、善は人間の中に「可能性」として伏在していると言う。そしてそれを開花させることができれば、周囲に共感の輪を広げ、善を実践することができると説く。
30年先の未来など予測できない、という声をよく聞く。もちろんクリスタルボールかタイムマシンがない限り、未来を的確に予測できるわけがない。しかし、想像することはできるはずだ。
もっとも、そのままでは未来はやってこない。ならば、みずからの手でつくり上げていけばよい。未来は待ち構えているものでも、正しく予測するものでもなく、みずから想像し、創造するものなのだ。
西田幾多郎はそれを「永遠の今の自己限定」と呼ぶ。未来は永遠に開かれている。それを実現するのは、自分自身の動的運動、すなわち実践である。そこで大切になるのは、現在、すなわち禅でいう「而今(にこん)」である。
永遠の現在の行為の積み重ねが未来を拓いていく。欧米型のバックキャスティングではなく、フォアキャスティング、すなわち現在の思いを基軸に、みずからの手で未来をつくり込んでいくことがカギとなる。
常に「現在」が起点となり、自分自身の信念に基づいてみずからを賭する(自己投企する)ことで未来をつくり続けていく。それがシン日本流の時間軸でなければならない。
では世界、すなわち空間軸をどうとらえればいいか。
再び西田幾多郎に立ち戻ってみたい。西田は、主体 対 客体という二元論を超えて、「他者のことを我がこととしてとらえる」視座の必要性を説く。そして、真にその境地に立てた時に、「善」を実践することができると言う。西田哲学の流れを汲む京都大学の出口康夫教授は、それを「われわれとしての自己(Self-as-We)」と呼ぶ。
そして、このシン日本流哲学は、静かに世界に広がり始めている。たとえば、禅(Zen)。筆者が教鞭を執る京都は、海外からの来訪者が絶えない。リピーターの多くは、禅寺に足しげく通う。スティーブ・ジョブズの禅への傾倒、そして京都愛好もよく知られている。いまも、シリコンバレーからプライベートジェットを飛ばして京都に来ては、枯山水の前で瞑想して帰国する著名なアメリカ人起業家の姿をよく見かける。
禅人気はインバウンドに留まらない。曹洞宗や臨済宗は、禅センターを欧米各地に建立しており、座禅は現地で静かなブームを呼んでいる。アメリカでは、とりわけ「2人の鈴木」が有名だ。一人は、仏教学者・鈴木大拙。『禅と日本文化(Zen and Japanese Culture)』を英語で出版(1938年)。禅の精神がみなぎる「日本流」を、世界に広めた。
もう一人が、曹洞宗の禅僧・鈴木俊隆。1959年、55歳で渡米し、西海岸に禅寺や禅センターを開設した。英語で書かれた主著『Zen Mind, Beginner’s Mind』(1970年)は、ジョブズをはじめ、全米で愛読され続けてきた。
禅に限らない。日本が大切にしてきた生活や文化は、飽くなき競争や終わりの見えない紛争を超える一つの有力なオルタナティブ(「別」)として、世界にますます注目されるのではないだろうか。
シン日本流経営も、日本の中だけで「ガラパゴス」化している場合ではない。シン日本流文化とともに、世界に布教する努力が、いまこそ求められている。共感の輪が広がることで、我々の花が一つひとつ開いていくことだろう。
◉構成・まとめ | 宮田和美 (ダイヤモンドクォータリー編集部)
【新刊のご案内】
名和高司氏の最新刊『シン日本流経営』(2025/2/18発行)は
こちらでご購入いただけます。
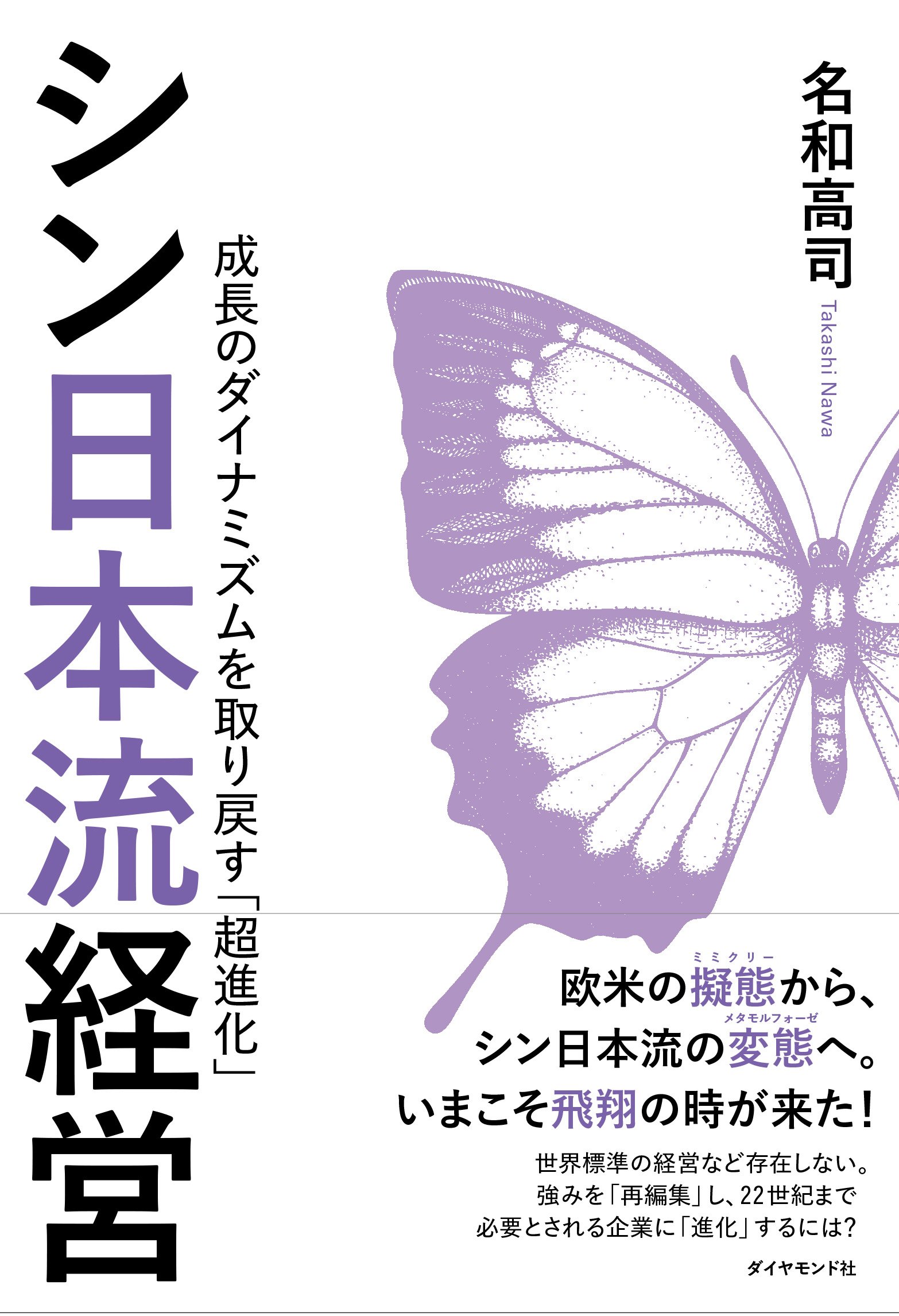

![[検証]戦後80年勝てない戦争をなぜ止められなかったのか](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/9/8/360wm/img_98a65d982c6b882eacb0b42f29fe9b5a304126.jpg)





