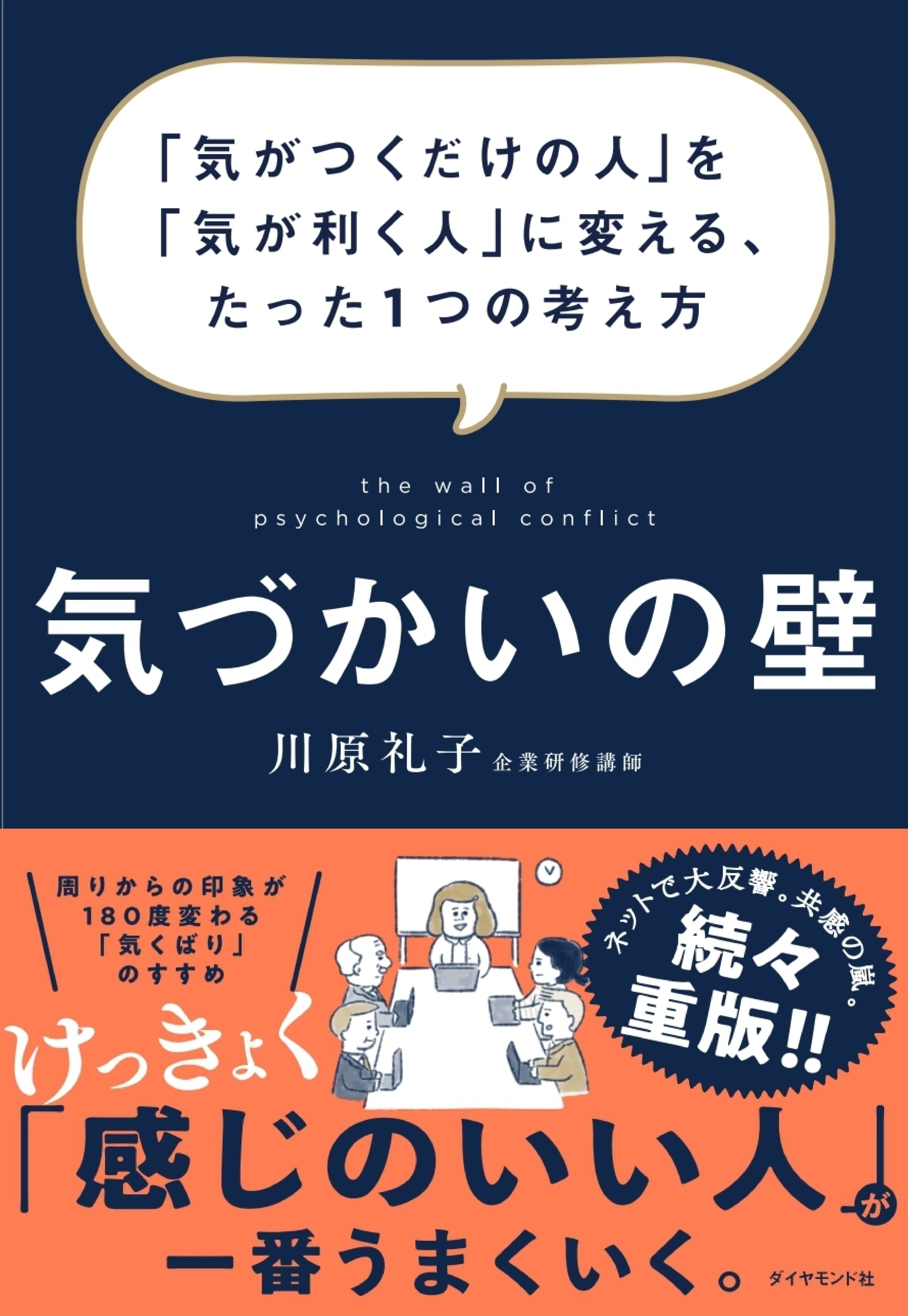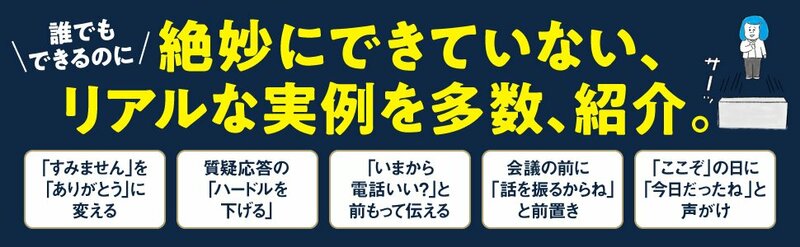「この人の電話なら受けてもいいかも?」と思ってもらう、感じのいい人の特徴とは?
それを語るのは、「感じのいい人」に生まれ変われるとっておきのコツを紹介する書籍『気づかいの壁』の著者・川原礼子さんです。職場で困っている人を見かけても、「おせっかいだったらどうしよう…」と躊躇したり、「たぶん大丈夫だろう…!」と自分に言い訳したり……。気づかいをするときには、つい「心の壁」が現れてしまい、なかなか一歩が踏み出せないことが、あなたにもあるのではないでしょうか? この連載では、「顧客ロイヤルティ」をベースに、ビジネスセミナーへの登壇やコミュニケーションスキルの研修講師を通して、全国200社・2万人以上のビジネスパーソンに向けて教えてきたノウハウを、さらにわかりやすくお伝えします。本稿では、本書には入りきらなかった「気づかいのコツ」について紹介しましょう。(構成/ダイヤモンド社・種岡 健)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
人の印象は最初の15秒で決まる
「〇〇さまのお電話でしょうか?」
見知らぬ番号からかかってきた電話に出て、こんなふうに自分の名前を言われたら、あなたはどう思うでしょうか。
実はこれ、私の実体験です。
「なぜ、私の名前を知ってるの?」と不信に思ったところで、さらに、「〇〇社ですが、いま、少しお時間よろしいでしょうか?」と続きました。
どのような要件かもわからないのに、時間があるなしを答えられませんでしたから、「どういったご用件でしょうか?」と聞くしかありませんでした。
結果的には、あるサービスの提案だったのですが、最初の印象が残念だったことから、早々にお断りをしました。
人の印象は最初の15秒で決まるとも言われています。
他のことをしているところを、遮るようにかかってくるのが電話。
「この人の電話なら受けてもいいかも?」と思ってもらうためには、電話をかけるときにも、気づかいが必要です。
知らないうちに「不快」にしてるかも?
電話をかけるときは、覚えておきたい6つのステップがあります。
① 名乗り ②相手確認 ③あいさつ ④理由 ⑤都合確認 ⑥お礼です。
―――――
私、〇〇社の川原と申します。(①名乗り)
おそれいりますが、山田さまでいらっしゃいますか?(②相手確認)
このたびは、私どものホームページからお問合せいただき、ありがとうございました。(③あいさつ)
ご返信する前に、2~3お聞かせいただきたいことがあり、お電話させていただきました。(④理由)
いま、5分ほど、お時間よろしいでしょうか。(⑤都合確認)
(いいですよ)
ありがとうございます。(⑥お礼)
―――――
という順番です。
「最初の名乗り」は、当たり前と認識している方は多いと思いますが、冒頭のように、理由を告げずに「いまいいですか?」と聞いてくる人は相当数います。
そして、知らない間に不快を与えています。
理由をつげずに、感じ悪さを与えているパターンが、もう一つあります。
それは、保留をするときです。
こちらから問い合わせをした際に、「少しお待ちくださいませ」と言って保留にされることはないでしょうか。
こんな時も、「では確認しますので、少しお待ちいただけますか?」と理由を言われれると、「私のために確認してくれる」という安心感が生まれます。
こうした、新人のころに学んだ「当たり前」が、気づくとおろそかになっていないでしょうか。
感じのいい人は、こうした「当たり前」をきちんとしています。
当たり前を踏まえたうえで、気の利く行動ができる人が、最終的に「あの人にお願いしたい!」と思われる人になっているのです。
(本記事は、『気づかいの壁』の著者・川原礼子氏が書き下ろしたものです。)
株式会社シーストーリーズ 代表取締役
元・株式会社リクルートCS推進室教育チームリーダー
高校卒業後、カリフォルニア州College of Marinに留学。その後、米国で永住権を取得し、カリフォルニア州バークレー・コンコードで寿司店の女将を8年経験。
2005年、株式会社リクルート入社。CS推進室でクレーム対応を中心に電話・メール対応、責任者対応を経験後、教育チームリーダーを歴任。年間100回を超える社員研修および取引先向けの研修・セミナー登壇を経験後独立。株式会社シーストーリーズ(C-Stories)を設立し、クチコミとご紹介だけで情報サービス会社・旅行会社などと年間契約を結ぶほか、食品会社・教育サービス会社・IT企業・旅館など、多業種にわたるリピーター企業を中心に“関係性構築”を目的とした顧客コミュニケーション指導およびリーダー・社内トレーナーの育成に従事。コンサルタント・講師として活動中。『気づかいの壁』(ダイヤモンド社)が初の著書となる。