気づかいは言葉づかいにも表れる。言うほうは気持ちよくても、耳にした人がモヤモヤしてしまう言葉は、避けたほうがいいだろう。そんな言葉について教えてくれているのは『気づかいの壁』だ。これまでおよそ200社、2万人のビジネスパーソンに向けてコミュニケーションスキル等の研修やセミナーを行ってきた著者、川原礼子氏は、サービスのプロではない一般のビジネスパーソンに向けて「ちょうど良い気づかい」のコツを教えてくれている。
本記事では、本書の内容から、言ってしまいがちだが「言われた相手がモヤモヤする言葉」について紹介する。(構成:小川晶子)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
プロっぽいが乱暴な表現
特定の業界、あるいは会社で使われる、独特の言い回しというものがある。
筆者の場合は、出版業界、ライター業界ということになるが、たとえば「原稿が上がる(原稿を上げる)」という言い方はその一つだ。執筆者が原稿を出版社などに渡すことを言う。
こういった業界特有の表現は、最初はちょっとかっこよく思える。プロっぽい。
だが、使う場面によっては乱暴な表現になると思う。
その業界に慣れていると無意識に使ってしまうが、実は相手はモヤモヤしているかもしれない。
実は筆者はかつて、「原稿はいつ頃上がってきますか」と聞かれてモヤモヤしたことがある。
だって、原稿は自然に上がってくるようなものではない。私が書く、ということだ。「原稿はいつ頃お送りいただけますか」でいいではないか。
小さなことだが、こういったモヤモヤはよくあるのだと思う。(自戒を込めて。)
本書には著者の川原礼子氏自身のこんなエピソードが載っていた。
店内はほぼ満席で、私たちを見るなり、スタッフさん同士で、「奥に入(い)れる?」と裏で話す声が聞こえてきました。
その後、ランチを食べられたのですが、私のモヤモヤは消えません。
このように、仕事に慣れてくると、つい無意識に乱暴な言葉を使ってしまうことがあります。(P.87)
あるあるではないだろうか。
言われた相手がモヤモヤする言葉3選
そのほか、本書に挙げられていた言葉の例(P.87)を見てみよう。
メールを投げるほか、作業を投げる、仕事を投げるなどがある。勢いよく仕事をしている感じはするが、受け取る側はモヤモヤするだろう。
「苦情を処理する」は正しい日本語ではあるが、苦情を言う側からすれば「処理」などと言われたくはない。事務的にさばいているというニュアンスがある。
「印象づける」「成果を出す」といった意味で使われている「爪痕を残す」だが、もともとは災害や事件による被害が後々まで残っているときに使う言葉である。勢いがあって面白いと感じる人もいると思う。でも、みんながそうとは限らない。
これらの言葉の共通点は、「人をモノ扱いしている」ということにある。
お客さまや商品のことを裏で悪く言うと、社内外の人にどう伝わるか、どう捉えられるかわかりません。悪口や陰口に必ずしもみんなが同調するとは限らないのと同じです。(P.88)
すべて丁寧な言葉づかいにする必要はないが、例に挙げたような言葉を言い換えるだけでも印象は変わるだろう。
あなたの業界で使いがちな言葉を振り返ってみるのもいいと思う。言い換えたほうが良さそうな言葉はないだろうか。
60点を目指せばいい
本書は、一般のビジネスパーソン向けに「気づかいのコツ」を教えてくれている。「乱暴な言葉を言い換える」のように、一つひとつは本当にちょっとしたことだ。
サービスのプロは、もっとハイレベルな気づかいが必要だろうが、普通のビジネスパーソンにはそこまで必要ない。完璧な気づかいをしようとすれば、する方もされる方も疲れてしまう。
川原氏は「60点くらいで十分」という。
普段あまり気の利いたことができないと思っている筆者のような人にとって、ハードルを下げてくれている本書はありがたい。
とはいえ、60点の気づかいだってたいしたものだ。
それくらい、あいさつレベルの簡単なことが、多くの人にとってできていないのです。(P.60)
普通のビジネスパーソンがすぐにできる、ちょっとした気づかいのコツが満載の本書を参考にしてみてはどうだろうか。
あなたの気づかいが周りに影響して、気持ちよく仕事ができる環境になっていくに違いないと思う。
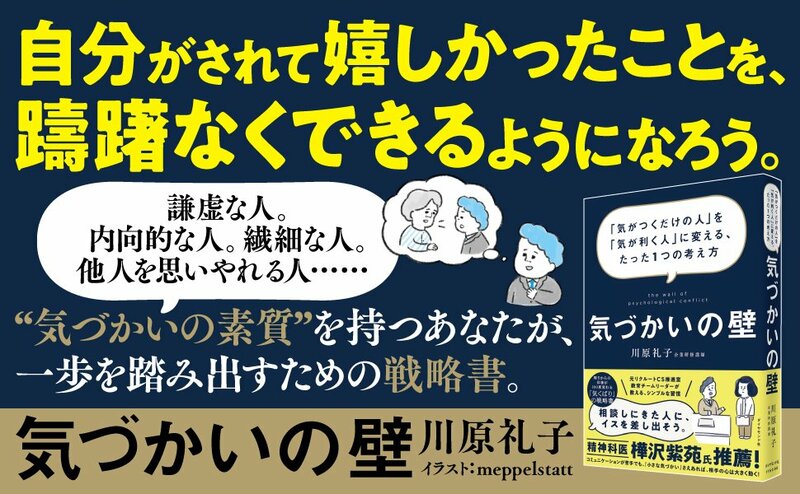
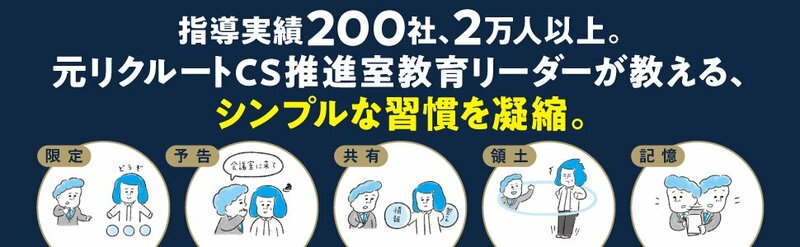
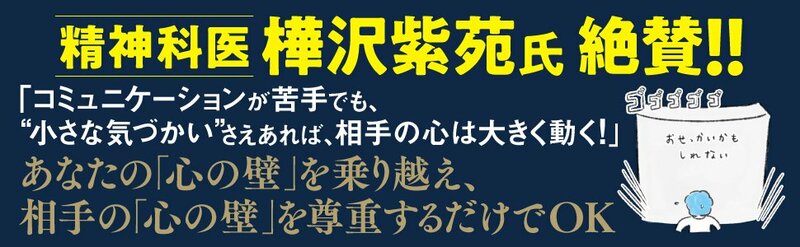
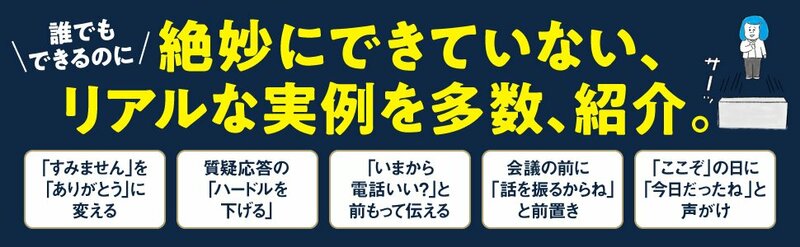



![クレーム対応で「上の人を出せ!」と言われたとき、「感じのいい人」はとっさに何と言い返す?[見逃し配信・4月第1週]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/9/1/360wm/img_c408de9ee6eb53a17af973770dfab532284421.jpg)