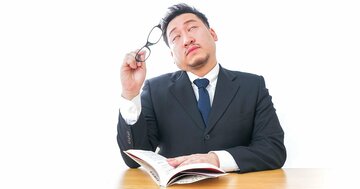3倍もの兵を持ちながら敗れた幕府軍の真実
「仕事が遅い部下がいてイライラする」「不本意な異動を命じられた」「かつての部下が上司になってしまった」――経営者、管理職、チームリーダー、アルバイトのバイトリーダーまで、組織を動かす立場の人間は、悩みが尽きない……。そんなときこそ頭がいい人は、「歴史」に解決策を求める。【人】【モノ】【お金】【情報】【目標】【健康】とテーマ別で、歴史上の人物の言葉をベースに、わかりやすく現代ビジネスの諸問題を解決する話題の書『リーダーは日本史に学べ』(ダイヤモンド社)は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、伊達政宗、島津斉彬など、歴史上の人物26人の「成功と失敗の本質」を説く。「基本ストイックだが、酒だけはやめられなかった……」(上杉謙信)といったリアルな人間性にも迫りつつ、マネジメントに絶対活きる「歴史の教訓」を学ぶ。
※本稿は『リーダーは日本史に学べ』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
水戸藩の精神と「尊皇思想」
徳川慶喜が出た水戸藩は、2代目藩主の徳川光圀(水戸黄門)以来、歴史書『大日本史』の編さんをライフワークとするなかで、天皇家を尊敬するようになります。
そのため慶喜は、父である徳川斉昭から水戸徳川家に代々伝えられた家訓として、「朝廷と幕府にもし争いが起きたら、幕府に背いてでも、朝廷に弓を引いてはならない」と教えられてきました。
幕府改革に乗り出す
時代は下り、第14代将軍・徳川家茂が亡くなり、慶喜が第15代将軍に就任しましたが、すでに幕府は長州藩との戦いに敗れ、その権威は地に堕ちていました。
この状況を打開しようと、慶喜は幕府の改革に着手。フランスの支援を得ながら神奈川・横須賀に造船所を設立したり、軍制改革を進めたりします。
弟・昭武と渋沢栄一をパリ万博へ
慶喜は幕府の使節として、弟の徳川昭武(1853~1910年)や家臣の渋沢栄一(1840~1931年)をフランスのパリ万博に派遣し、西洋の先端技術や民間が力を発揮する社会に触れつつ、諸外国との交流を深めようとしました。
平和的に政権を返す「大政奉還」
しかし、幕府の打倒を目指す薩摩藩の動きは止まりませんでした。そのため、慶喜は幕府から朝廷への政権移行を平和裏に進めるため、朝廷への政権返上「大政奉還」(1867年)に踏み切ります。
慶喜としては、朝廷に政権を返上したうえで、その新しい政権への参加を目指していたのでしょう。
王政復古の大号令――クーデター勃発
しかし、新しい政権からも慶喜を排除したい薩摩藩は、明治天皇の名で王政復古の大号令(1867年)を発したことによるクーデターを実行して、朝廷を押さえ、慶喜を排除し、領地の返還や官位の返上を求めます。
鳥羽・伏見の戦いへ
このとき、慶喜は京都にいましたが、朝廷・薩摩藩と幕府が衝突することを避けるため、幕府軍を連れて大坂に移動します。
しかし、王政復古の大号令など薩摩藩の動きを許せないという幕府内の声は大きく、幕府軍は大坂から京都に向けて進軍し、とうとう薩摩藩などの軍(新政府軍)と鳥羽・伏見の戦い(1868年)で衝突します。
幕府軍、数で勝るも敗北
新政府軍約5000人に対して、幕府軍は約1万5000人と、幕府軍のほうが圧倒的優勢だったものの、新政府軍は最新式の兵器を備えて士気も高く、またリーダーの西郷隆盛自身が前線に立つなど、リーダーシップでも優位に立ちました。
慶喜、戦場に出ず
一方、幕府軍のリーダーである慶喜は、前線に立つようなことはしていません。加えて、新政府軍の切り崩し工作もあり、淀藩や津藩といった親幕府と思われていた藩も幕府を裏切ります。
極めつきは、新政府軍が官軍(天皇の軍隊)であることを示す錦旗を掲げたことでした。これにより、幕府軍は賊軍(天皇の反逆軍)という位置づけになったのです。
尊皇の教えに揺れる慶喜の心
これは、天皇を尊敬するように育てられた慶喜には耐えられないものでした。
※本稿は『リーダーは日本史に学べ』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。