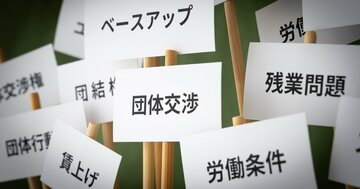なぜ輸入物価が低下したにもかかわらず、消費者物価が低下しないのか?その理由は、企業が輸入物価の下落による原価の下落を、販売価格の下落に還元しなかったことだ。
筆者はこれを「強欲資本主義Ⅱ」(編集部注/「強欲資本主義Ⅰ」はインフレに便乗して企業利益を増大させること。「強欲資本主義Ⅱ」はその後、輸入物価の下落を還元しないこと)と名付けた。
ところが、2023年の春闘頃からもう1つの動きが始まった。それは、賃上げが販売価格に転嫁されたことだ。
少なくとも大企業については、それが行なわれただろう。また、食料や宿泊費については、中小零細企業も含めて、販売価格への転嫁が行なわれたと考えられる。こうして、賃上げが消費者物価に影響を与えるようになったのだ。
大企業の賃上げと連動して
私たちの生活が苦しくなる
つまり、これまでのように海外のインフレが国内の消費者物価に転嫁されるのではなく、国内での賃上げが消費者物価に転嫁されるというプロセスに変化してきている。これが第3段階だ。これを「強欲資本主義III」と呼ぶことができるだろう。
これが望ましいかどうかについての判断が重要だ。日本政府は、このプロセスを進めることが望ましいとして、中小企業も価格転嫁ができるよう、企業を指導している。政府や経済界以外にも、このプロセスは「物価と賃金の好循環」であり、望ましい動きであるとして、積極的に進めるべきだとする意見が強い。
こうした状況を背景として、24年春闘における賃金上昇率は、さらに高まった。
強欲資本主義IIIのプロセスも、玉突き的な物価上昇、つまりコストプッシュ・インフレであるという点では、従来からあった輸入物価高騰の消費者物価への転嫁と同じだ。
ただし、違いがある。それは、インフレが加速する恐れがあることだ。なぜなら、最初に行なわれた賃金引き上げの効果が、物価上昇によって薄められてしまうからだ。だから、さらに高い賃金引き上げが求められる。こうして、物価上昇と賃上げのスパイラルが発生してしまう危険がある。
これは、1973年に生じた第一次石油ショックで、世界の多くの国が悩まされた現象だ。原油価格が上昇するために輸入物価が上昇し、国内物価も上昇する。これに対応するため賃金を引き上げる。
労働組合が職種別組合になっている欧米諸国、とくにイギリスでは、この動きがとりわけ顕著に生じた。その結果、イギリス経済は危機的な状況に陥ってしまったのである。