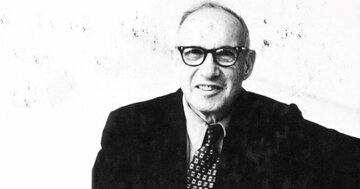ここでマネジメントの人間は第3の石工であり、問題は第2の石工だと、ドラッカーはいうのです。その理由として、熟練した専門技術は不可欠であるとしたうえで、「だがスペシャリストは、単に石を磨き脚柱を集めているにすぎなくとも重大なことをしていると錯覚しがちである。専門能力の重要性は強調しなければならない。しかし、それは全体のニーズとの関連においてでなければならない。」(『マネジメント』[中]p.70)と述べています。私たちの組織にも、多様な石工が働いています。
第3の石工のように全体を見て公的な意志を持って働き、チームをリードすることが大切です。自己の便益以上に、より公的な心構えを持ち仕事をすることが大切なのです。
オーケストラに学ぶ
持続する組織の仕組み
有名企業の働きが顧客や社会ニーズに反して組織が機能不全となり、社会的な不祥事が発覚し経営に支障をきたす例が後を絶ちません。一方で、時代を超えて持続する組織の1つにオーケストラがあります。
オーストリアのウィーンで生まれ少年時代を過ごしたドラッカーは、古典的な音楽が日常にあった社会に育まれました。この環境で育まれた感性は、彼が体系化したマネジメントの基本と原則の中にも表れています。
例えば、『マネジメント』[中]p.24の中で、マネジメントの仕事は、「第一に、部分の総和よりも大きな全体、すなわち投入した資源の総和よりも大きなものを生みだすことである。それは、自らのビジョン、働き、リーダーシップによって、多くの楽器をまとめあげるオーケストラの指揮者に似ている。だが指揮者が手にしているのは、作曲家の手になる楽譜である。これに対し組織のマネジメントは、指揮者であると同時に作曲家である。」と述べています。
スペシャリストや多様な働き方が増える今日、オーケストラを参考に、良い組織を支えている仕組みは何かを考えてみることも大切です。
まず、第1に楽譜があることです。楽曲全体の楽譜のことを総譜(トータルスコア)といいます。数十人のオーケストラであれば、バイオリン、クラリネット、フルートなどの演奏者はパートというチームになります。
各楽器演奏者は、総譜の中で役割に応じたパート譜(パートスコア)をもとに、指揮者の指揮に合わせて演奏します。パートリーダーは総譜に調和したパートスコアを指揮者と相談して書き、本番演奏で最高のチーム演奏を披露するために、各演奏者を惹きつけ、やる気を出させ、強みを結集し、楽曲を奏でることで、聴衆に感動を与えることができるのです。