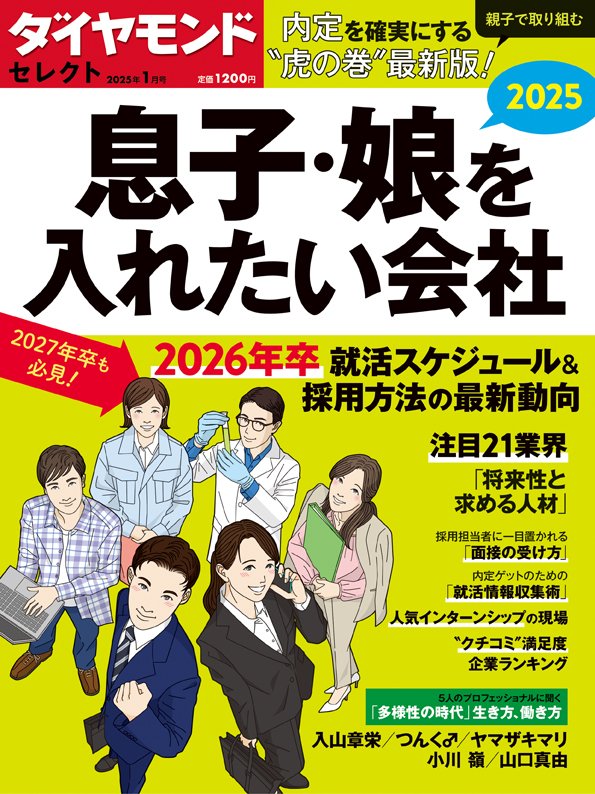ヒュンダイのマーケティング力
BYDのデザイン性
今、自動車メーカー各社が注視しているのがインド市場である。すでに人口は中国を上回り、今後数年で世界最大の自動車市場に成長する可能性が高い。
日本メーカーではスズキ(マルチ・スズキ・インディア)が圧倒的なシェアを持つが、ヒュンダイが猛追しており、現地に最適化した車両・価格戦略で急成長している。
特筆すべきはヒュンダイのマーケティング力である。同社は韓国の大学と連携し、現地の消費者ニーズを徹底的に分析してから参入を決めている。
韓国市場は160万台程度と小規模であるため、海外進出が必須であり、それ故にマーケティング戦略には磨きがかかっているという背景がある。
これに対し、日本メーカーは国内市場の規模に甘え、海外戦略においてはやや後手に回っている印象がある。
日本では年間460万台が安定的に売れるため、国内だけでも一定の収益を確保できてしまうからである。しかし、国内市場は高齢化と人口減少により縮小傾向にあるため、今後は海外戦略がますます重要となる。
海外メーカーに目を向けると、中国メーカーのBYDも世界市場での存在感を高めている。日本市場でも若年層を中心に浸透しつつあり、特に女性ユーザーの支持があるという。
「BYDはドイツ車メーカーからデザイナーを引き抜き、欧州テイストの洗練されたデザインを採用。価格の安さも相まって、若い世代の心をつかんでいる」(饗場氏)
ただし、40代以上を中心に「中国製」への警戒感は根強く、安全性や信頼性の面でまだハードルは高い。今後この壁を乗り越えられるかどうかが、中国メーカーの本格普及の鍵を握る。
「競争」から「共創」へ
需要が高まっている人材は?
このような流れを受け、自動車業界では「理系」だけでなく、「文系」人材、とりわけマーケティング人材の需要が急速に高まっている。
EVやPHVといった新技術をいかに市場に受け入れてもらうか、消費者心理に沿った製品・価格設計をいかに行うか。これはまさにマーケティングの力にかかっている。
トヨタが現在の利益の大半を北米で稼いでいることを見ても、グローバル市場での適応力と戦略構築力が、今後の企業の明暗を分けるだろう。
日産・ホンダの提携は、その象徴的な一歩であり、日本の自動車業界が「競争から共創」へと転換しつつある現実を物語っている。
EV時代の覇権争いは、単なる技術力の勝負ではなく、マーケティング、組織力、現地適応力を総動員した総合戦となっている。自動車業界の次なる主役は、果たして誰なのか。注目の時代が始まっている。