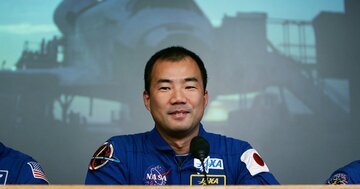「今、仕事何してるの?」がお決まりのパーティートーク。
「前の仕事は辞めて、仕事を探してるんだ」みたいに、仕事探しのためにソーシャライズ(人的交流)するのが当たり前の社会になっています。
一方、日本は会社組織が優先される“会社社会”ですから、会社を辞めた途端、会社主催の懇親会などには出られないという現象が起きますよね。出身大学の同窓会は出られるのに、会社の同窓会は、中途退職者は出にくいものです。
宇宙飛行士にフォーカスしてみると、アメリカでは、軍人出身と民間出身に大きく分けられます。
軍人出身の退役宇宙飛行士だと、その多くは空軍や海軍などの軍属に戻り、組織の中でキャリアを積み重ねていくことが非常に重要視されます。
このほかにも、大学教授など公的機関でポジションを得る人や、宇宙関連企業など民間企業へ転身するなどバラエティに富んでいます。
どちらにしても、宇宙飛行士になった時点で、すでに自分自身のキャリア形成の一歩ととらえていて、さらなるキャリアに踏み出すためのステップストーン(踏み石)だと明確にしている人が多い。ジョブ型雇用の社会らしいですね。
総じて、アメリカの宇宙飛行士たちは「定年までNASAにいるなんてありえない」と明確に言っているし、実際、そうなっている。
そもそも、アメリカで宇宙飛行士として生活を送る期間はだいたい10~15年ぐらいが圧倒的に多い。私の在籍期間は25年。アメリカの同僚たちに言わせたら、もう長すぎたのです。
「45歳定年制」で
人材の流動化が進む
2021年9月、サントリーホールディングスの新浪剛史社長が、経済同友会の夏季セミナーで「45歳定年制を導入し、個人が会社に頼らない仕組みが必要だ」と提言し、SNSなどで批判を浴びました。
セミナーはコロナ禍のためオンラインで開かれ、ウィズコロナを見据えた企業の役割について提言する中で飛び出しました。
この中で新浪氏は、アベノミクスについて振り返り「最低賃金の引き上げを中心に賃上げに取り組んだが、結果として企業の新陳代謝や労働移動が進まず、低成長に甘んじることになった」「日本企業はもっと貪欲にならないといけない」と語り、日本企業が企業価値を向上させるため「45歳定年制」の導入によって人材の流動化が進むと述べています。