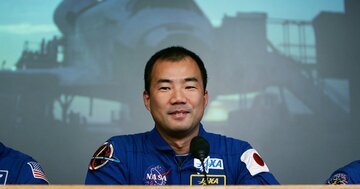社風なるものが生まれ、個人よりも集団の協調性を重視する昭和の謎ルールみたいなものに支配されているのです。
こうした企業集団に入社し、組織体質に染まってしまうと、もう外へは出て行けない。その結果、会社の業績を上げることよりも、出世競争によって得られるメンバーシップ内部の地位の獲得にばかり関心を寄せてしまいがちです。
しかも、日本企業の管理職は外部登用が少なく、ほとんどの場合は年次に従って昇進しますから、前任者から社風とか謎ルールとか空気感みたいなものをそのまま引き継ぐことが良しとされ、企業風土を維持する役回りを担います。
欧米流のジョブ型雇用が
多様性組織を実現させる
こうした共同体の中では、上司はあたかもシャーマンのように振る舞い、部下たちは無言でそれに従っているのです。
一方、欧米では「ジョブ型雇用」が当たり前です。
個々の業務において要求されるスキルを持った人たちを組織の内外問わずに採用し、必要なセクションに当てはめていく雇用形態です。
ジョブ型雇用の場合、外部から採用するケースも多くなりますから、組織に対する社員の帰属意識は低い。あくまでも、自分のスキルや経歴に見合った収入と業務が得られるかどうか――それが、その会社に留まる決定的な要因になっています。
ですから、日本の会社のように大学を出たばかりで実務能力のない若者を遊ばせておいたり、長い年月をかけて幹部育成をしたりするなんてことは少ないのです。
ジョブ型雇用では、管理職の登用も組織内外を問わず、その時点でのジョブ・ディスクリプション(業務要求、job description)に合致する人材を充当させます。初日から成果が出るような能力ある人を雇うのです。いってみれば前任者との継続性よりも、どのようなイノベーションを会社にもたらし、新しい価値創造ができるかが求められるのです。
このような管理職登用は、転職する側にとっても有益です。ジョブ・ディスクリプションが明文化されているので自分に期待されていることがはっきり分かる(要求の透明化)、社外から流入することの障壁が少ない(競争の公正化)、そして採用された後は自分のスキルに自信を持って活動できる(心理的安全性)、これらが相互作用することで多様性組織の実現にも大きく寄与するでしょう。