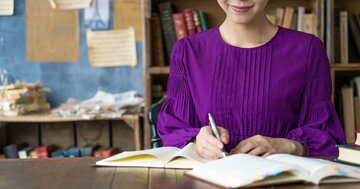なので、私は夜に勉強が思うように進まないとか、つまずいてしまったとか、そうなったら「集中できていないから、いくら考えてもどうせわからない」とすっぱりあきらめて、早めに寝てしまうようにしていました。
私の体感的に、夜に勉強をしていてわからないことは、おそらくそれから3時間、4時間やってもわからないままが多かったと実感しています。
脳科学的にも、実体験的にも、朝までしっかり寝て、脳と身体を休めて、朝起きてもう1回やったら「わかった!」ということがあります。
人間は寝ている間にも頭の中で思考したり、寝る前にやったことを脳が整理したりしています。そのため、次の朝になると考えがまとまって、すんなり理解できるようになっていたことは、実際に多々ありました。
ですから、夜の勉強はあまり効率を期待せず、早起きして朝の勉強に集中したほうが効果的です。
「朝ご飯を食べるまで」が
勉強の“勝負時間”
一般的に早起きといっても時間の使い方はいろいろありますが、私の場合は、「朝起きてから朝食を食べるまでの時間に勉強する」というルーティンにしていました。
試験まで1年くらい前、高校3年生になってから少し経った頃に「早起きできるようにしないとヤバい」と思い立って始めたのですが、とても成績が伸びました。
朝ご飯を食べる前に勉強するのは、食事をすると血糖値の変化で少し眠くなってしまい、効率が落ちる傾向にあるからです。
ですから、例えば朝の8時にご飯を食べるなら、6時頃には起きて、2時間勉強するといった形にしていました。
集中力や体力を保つために
とにかく寝ることを優先
私の早起きのポイントとして、就寝から起床までの時間を計算することを心掛けていました。受験生のとき、私は集中力や体力を保つためにも7~8時間は眠らないとダメだと意識していましたから、いくら早起きしたとしても、寝るのが遅かったら大事な睡眠時間が確保できなくなります。