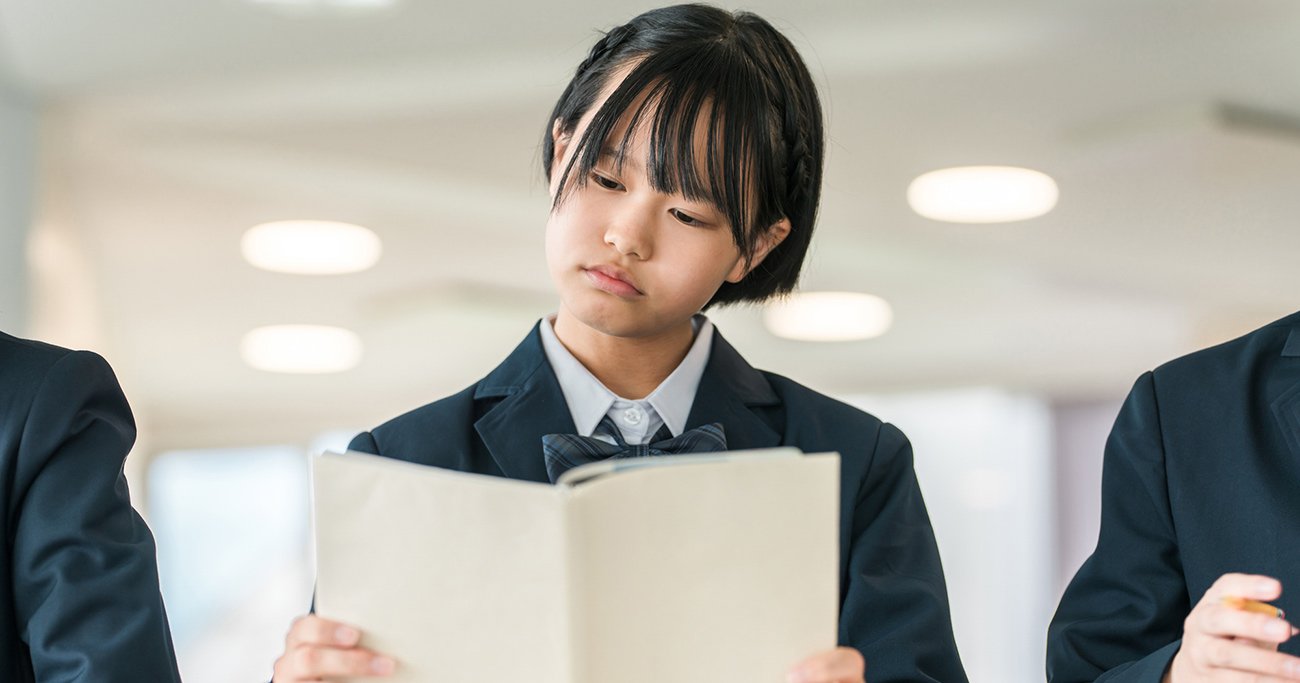 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
受験の「苦手科目」は学生のメンタルを落ち込ませる厄介なもの。一方で「得意科目」といえるほど点数がとれる科目もない…と、投げやりになる人もいるだろう。しかし、東大受験と司法試験を一発で合格した弁護士の越水遥氏によると、合格への第一歩は自分の“得手不得手”を自覚することだという。同氏が勧める「苦手科目」と「得意科目」の見極め方とは。※本稿は、越水 遥『最短で最高の結果が出る逆算式勉強』(フォレスト出版)の一部を抜粋・編集したものです。
どんな人にだって
苦手科目はある
苦手科目があることで不安になっている人は多いと思います。自分の弱点であり、苦手科目の有無が受験の合否を左右するようなイメージもありますから、苦手科目があってはいけないと悲観してしまうことでしょう。
しかし、苦手科目を克服しようとしても、なかなかうまくいかないものです。苦手なのですから、当然といえば当然なのですが、克服できないと余計に焦りが出てしまい、悲観的な気持ちに拍車がかかってしまうでしょう。
そんな受験生たちに断言しますが、誰しも苦手科目はあります。苦手科目がない人なんていないので、条件はみんな同じですから悲観する必要はまったくありません。
何もかも完璧にやる必要はなく、しっかり押さえるべきツボを押さえて、最終的に試験に合格することができればいいのです。
苦手科目があると、どうしても「この科目で○点しか取れなかったらどうしよう」と悩んでしまい、メンタル的な足かせにもなります。
試験本番は「自分が一番」だと思って受けてほしいのですが、そういう気持ちになるのも、苦手教科の試験だと難しくなってきます。
苦手科目のせいで
落ち込むのはNG
しかし、苦手科目がない人なんていません。すべての科目を完璧にできる人なんて、私も今まで見たことがありません。みんな、何かしら「できないこと」「苦手なこと」を抱えているのです。
ですから、苦手科目があるからといって、それにメンタルが引きずられて試験や勉強のマイナスになってしまうのは、非常にもったいないことです。
とはいえ、苦手教科のせいで試験に合格できなくなってしまったら元も子もありませんから、何かしらの対策をしなければいけません。
このとき、よくあるのが「とにかくがんばって苦手科目を克服しよう」「勉強時間をたっぷり使って苦手をなくそう」といった作戦です。これはある意味で王道ですし、長期的な視点でいえばプラスになるでしょうが、短い期間の勝負である受験ということでいえば、この作戦はマイナスにしかなりません。







