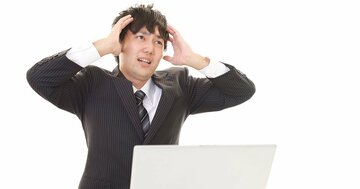ビジネス環境や働き方が大きく変化する中、働く現場では「人と組織」をめぐる課題が複雑化している。近年では、個人の学習・変化を促す「人材開発」とともに、「組織開発」というアプローチが話題になっており、『いちばんやさしい「組織開発」のはじめ方』(中村和彦監修・解説、早瀬信、高橋妙子、瀬山暁夫著)のような入門書も刊行された。今回は、こうした「人と組織のあいだに渦巻くモヤモヤ」に正面から切り込んだ話題作『冒険する組織のつくりかた 「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』の著者であり、気鋭の組織づくりコンサルファームMIMIGURI代表でもある安斎勇樹さんに、「目標を最後まで貫くことがかえって組織の柔軟性を奪う理由」について話を伺った。(企画:ダイヤモンド社書籍編集局)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「やり抜き方」が問われている
――「物事は一度はじめたら最後までやり抜くべき」という考え方はとても立派だと思います。ですが、いまの職場では、「どんなに違和感があってもとにかくやり抜こう」という風潮が強すぎて、すごくモヤモヤしています。
安斎勇樹(以下、安斎)「GRIT=やり抜く力」が注目を浴びてから「最後までやり抜くべし」という価値観は、世の中にいっそう広がったように思います。ぼくも粘り強く取り組む姿勢自体はすごく大事だと思っていますが、問題は“どうやり抜くか?”をしっかり考えることだと思いますね。
たとえば、子どもの頃に「サッカー選手になる」と夢を掲げて、それを中学・高校とあきらめずに努力した結果、プロになれました――という話。これは目標が揺るがず、外部環境もそこまで変わらない中で、最後までやり抜くことが有効だった例ですよね。
でも今の時代って、外部環境の変化がすごく速い。目標を立てたときは妥当だったものが、1年後には通用しなくなることもある。
たとえば「YouTubeで3年以内にトップを取る」と目標を立てたとする。ところが、その間にTikTokが台頭してくるとか、プラットフォームのトレンドそのものが変わってしまう。そんな時代に「立てた目標を最後まで貫かなきゃいけない」と考えてしまうと、軌道修正ができなくなる。それがいちばん危険だと思うんです。
柔軟な目標から「冒険」が始まる
安斎 だから大事なのは、「なぜその目標を立てたのか?」という“上位目標”を確認しておくこと。
その目標に込めた自分の価値観や本質的に大切にしたいことを見直して、“具体目標”のほうは柔軟に変えていけばいい。
目標ってそもそも多層的なものなんです。目の前の業務目標もあれば、年間目標、キャリア目標、人生目標……と入れ子構造になっている。
下位の目標ばかりを正義だと思いすぎると、上位にあるルールや価値観を無視することにもなりかねない。
先ほどの例で言うと、YouTubeにこだわらなくてもPodcastでもいいし、目的に合致するなら別の手段でもいい。そういう柔軟なやり抜き方が、これからの時代には求められていると思います。
「与えられた目標を決められたやり方でそのままやり抜く」という姿勢を「軍事的GRIT」と呼ぶとしましょう。
他方で、「海賊王になる」みたいな上位目標があって、そこに至る具体的ルートはわからないけど、とにかく好奇心に突き動かされてあきらめることなく進んでいく、という「やり抜き方」もあります。
こういう「冒険的GRIT」のほうが、現代にはフィットしているんじゃないかと思います。