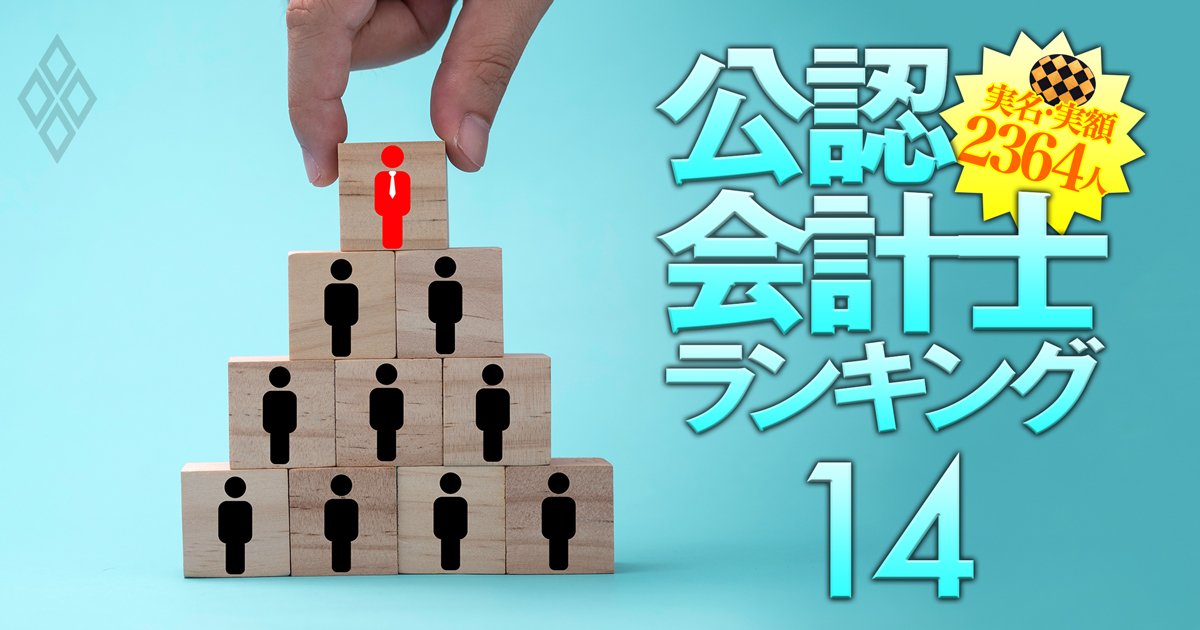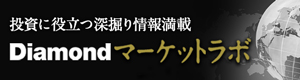賃金上昇の転嫁でサービス価格高騰
実態は賃金と物価の「悪循環」
企業は、賃金上昇分を価格に転嫁する動きを強めており、この傾向は、外食や宿泊をはじめとするサービス価格に顕著に見られる。サービス価格は、賃金上昇によって直接に影響を受けるからだ。
ただ、このメカニズムはサービス産業に限らず、より広範に生じていると考えられる。
賃上げ転嫁による物価上昇は、消費者物価指数では、さまざまな項目にその影響が分散されている。そのため、どれか特定の項目が問題だと指摘することが難しい。
ただ、最近時点の消費者物価の上昇の多くの部分は、賃金上昇を背景とした企業の価格転嫁によるものであり、今後もこの傾向が続くと考えられる。
賃上げの販売価格への転嫁が無制限に行われれば、賃上げをすれば物価が上昇することになる。そして、物価が上昇するために賃金を引き上げざるを得なくなる。こうして賃金と物価の高騰が際限もなく続く。賃金と物価の「悪循環」が生じる。
実質賃金が上昇しないために消費が増えず、GDPも停滞する。つまり、経済はスタグフレーションに陥る。日本はすでにその瀬戸際に立っていると考えざるを得ない。
物価対策は便乗値上げ監視や生産性向上の支援に
バラマキのガソリン価格抑制の補助は撤廃を
ところが、政府の物価対策は22年ごろの情勢を前提にした物価対策であり、ガソリン価格や電気・ガス料金等、輸入物価の上昇に起因する物価上昇を抑えることを目的としている。
そして、原油価格の低下にもかかわらず、従来の方向をさらに強めようとしている。政府・与党は、ガソリン価格につき、定額の値下げ方式を導入しガソリン価格が下がっても補助を続けられるように制度を改正する。また、電気・ガス代の補助を7月から再開する。
こうしたことでは、最近の物価高騰はコントロールできない。これを根本から見直すことが必要だ。
やるべきは、賃上げの価格転嫁のチェック、特に便乗値上げ対策だ。そして根本的な施策としては、生産性向上による賃上げを実現できるような政策を行うべきだ。
現在の物価対策で特に問題なのはガソリン価格抑制の補助だ。この政策は、国民のためになるから行っているのではなく、いったん導入したバラマキ政策から脱出できないからという、ただそれだけの理由で続けられているとしか考えようがない。今すぐにやめることが必要だ。
(一橋大学名誉教授 野口悠紀雄)