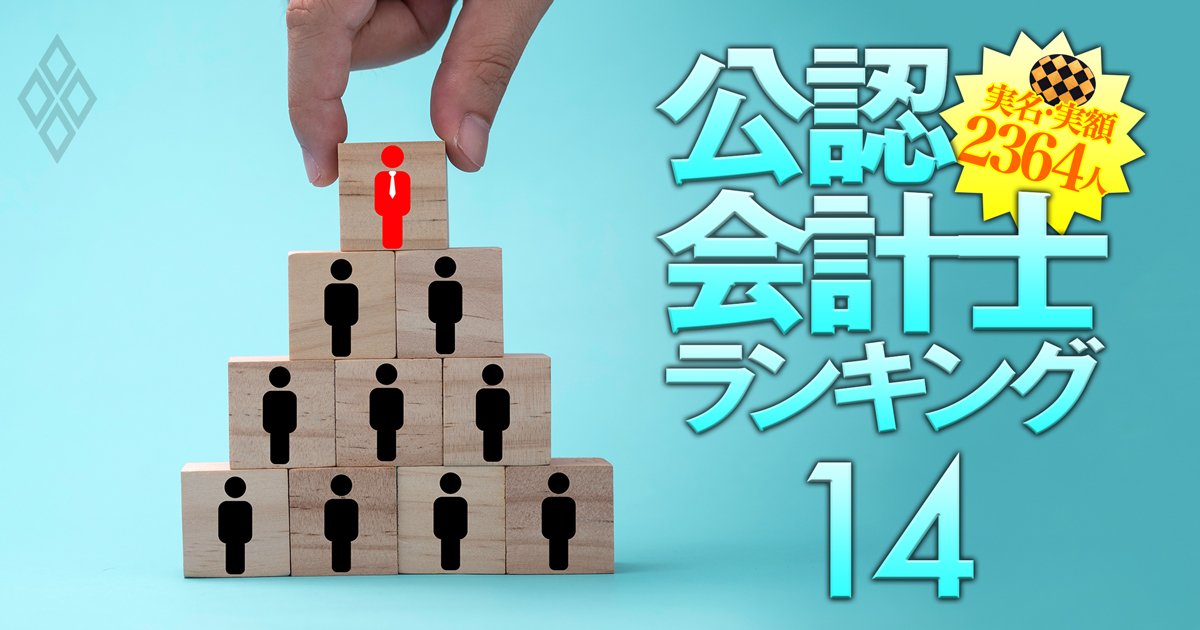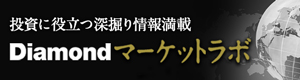コメ価格は前年比92.1%の上昇
だがその分を除いても2.5%の上昇率
直近3月をはじめ、このところの消費者物価の高騰は、コメの価格が上昇したことだと説明されている。
項目別の上昇率と寄与度を見ると確かにその通りであり、コメ価格の対前年同月比は92.1%と非常に高い値だ。これは過去最高値だ。しかも、6カ月連続で過去最大を更新した。
寄与度も0.5%ptと高い。コメ価格上昇がなかったとしたら、3月の消費者物価指数の上昇率は2.5%になっていたはずだ。
コメのような基礎的消費財の価格高騰は、所得の低い家計に対して非常に重い負担になる。ガソリン価格の上昇は、所得が比較的高い家計に重い負担になるのと対照的だ。
しかも、本コラム『トランプ相互関税に日本は反論すべきだが、「コメ政策の根本的見直し」が大前提』(2025年4月10日付)で指摘したように、コメの国内価格をコントロールするために、政府はミニマムアクセス以外の輸入に高関税をかけてシャットアウトし、日本のコメ市場を世界の市場から隔離している。
これは極めて大きな輸入障壁であり、アメリカが関税交渉に関連して問題としている。
4月16日に行われた日米関税協議でも、アメリカ側からコメ問題についての言及があったという。
アメリカは、日本がコメに700%の関税をかけているとかねて批判していた。700%は間違いだが、高率の関税をかけていることは間違いない。
コメ価格がこのように上昇したのは、24年の天候不順のために収穫量が少なかったからだが、それだけではない。
政府は備蓄米を保有しているが、この目的は、需給が逼迫した場合に価格の高騰を避けることだ。まさに今回のような事態に対処することが目的で備蓄米を保有しているはずなのだが、昨年の夏にコメが不足し、店頭からコメがなくなるという異常事態が起きたにもかかわらず、政府は備蓄米の放出を行わなかった。
今年の3月になってからやっと放出を始めたのだが、価格に影響を与えることができなかった。放出量が極めて少なかったからだが、その後行われた農水省の追跡調査によると、3月10~12日の放出分14.2万トンのうち、月末30日までに小売店に届いたのは、わずか0.3%でしかなかった。これでは効果がないのも当然だ。
物価上昇要因が輸入から国内に変化
3月の輸入物価指数の対前年比は-1.6%
以上のように、コメ価格上昇率は大きな問題だが、仮にコメ価格高騰がなかったとしても、消費者物価は2.9% というかなり高い値になる。つまり、「コメだけが物価高騰の原因」とは言えないのだ。
コメ価格高騰と並んで大きな問題は、今までなかった物価高騰要因が登場していることだ。
物価上昇の原因はここ数年で大きく変わってきている。
22~23年ごろには、ロシアのウクライナ侵攻や円安の影響で、エネルギー・食料など輸入品価格が急騰した。これが国内物価を押し上げたので、「輸入インフレ」と呼ばれた。
しかし、 最近の傾向(24年後半~25年)を見ると、急激な円安は止まり、資源価格も安定したため、輸入価格の上昇率は低下している。
円ベース輸入物価指数の対前年伸び率を見ると、24年12月は-0.6%、25年1月は1.5%、2月は-1.7% 、3月は-1.6%となっている。
このように、伸び率がマイナスになっている月のほうが多い。だからこれまでの傾向が続くなら、国内物価が下落して当然なのだ。
それにもかかわらず、消費者物価が上昇しているのは、コメ以外の国内要因によって物価が上昇しているからだ。
その要因とは、賃上げ分が売上価格に転嫁されていることだ。最近の日本の消費者物価の上昇要因は、輸入品価格の上昇から国内要因へとシフトしつつある。