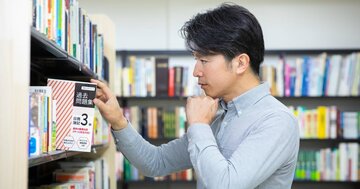写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
2025年4月から育休中の給付金が増額された。政府は「育休取得中に金銭面でサポートするから安心して子どもを産んでほしい」と促す狙いがあるのだろうが、取得する当事者にとってはメリットがある半面、職場の負担は増す。会社の人事・総務部は手続きのために2カ月に1度ハローワークに申請する必要が生じるなど、人手不足の中で仕事が増すからだ。その結果、心ない言葉で出産退社を促す人事・総務部も増えてしまっている。育休給付金増額と男性育休の光と影を考える。(生活経済ジャーナリスト 柏木理佳)
夫は大学院を休学、妻は育休で
200万円の貯金が底をついた
これまで、原則、1年間の育児休業中にもらえる給付金(育児休業給付金)は、最初の半年間は賃金の67%で、その後の半年間は賃金のわずか50%でした。
「育休中の給付金は月10万円。それだけでは生活費を賄えず、貯金を切り崩すうちに底をつきました」と語るのは、町田洋一さん(仮名・47歳)。町田さんは仕事を辞めて大学院に通い始めたばかりの頃に第1子が生まれました。
出産後、会社員だった妻は育休を取得。町田さんも大学院と子育ての両立は難しそうだと思い、休学を決めました。
「妻も働いているし、貯金は200万円も貯まっていたから、生活費はなんとかなると思っていました。それが、まさか。育児にこんなにお金がかかるとはと正直驚きました……」
妻の収入は月額20万円ほどありました。それでも毎月、オムツ代が8000円以上、ミルク代7000円以上、それに肌着や衣類のほか、ベビーシッター費用がかかり、これらを合わせた固定費は月5万円以上にのぼりました。
さらにベビーカー4万円、ベビーベッド3万円。赤ちゃんがアトピー性皮膚炎を発症したため、床を絨毯からフローリングにリフォームして30万円。赤ちゃんを抱っこしながら外のベランダに洗濯物を干すのが大変で、ドラム式洗濯機を購入し、15万円。電動自転車8万円……と次々に予想外の買い物が発生しました。
1年間で貯金120万円が減り、その後も色々と出費が増え、2年もたたずに貯金が底をついたそうです。
町田さんだけではありません。育児給付金を受け取っても、「足りない」と感じる人は多いでしょう。いったい、いくら必要なのでしょうか?