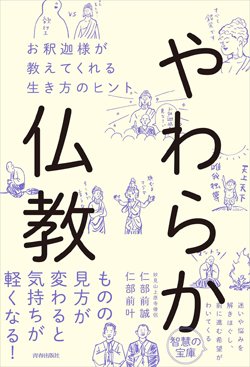その証拠に、仏典には自身が欲望と向き合うシーンがたびたび出てきます。教えを説いているとき、欲望が悪魔という姿になってぬっと現れ、その悪魔が「おいっ」と邪魔してくるという描写です。
その修行体験から、弟子たちにも「欲望の輪廻から脱却するにはこれまでと同じ生活では無理だ。煩悩を滅しなさい」と説いたのです。
「欲望のコントロール」が仏教の一大テーマ
「煩悩を滅する」というと、「欲望を完全にゼロにすること?」と思うかもしれませんが、仏教が本当に伝えたいのは「欲のコントロールをしなさい」ということです。
お釈迦様は欲望のコントロールを完全に達成しましたが、欲望自体がなくなったわけではありません。
考えてみてください。仮に欲望や煩悩がゼロになったら、世捨て人のように精彩を欠いた人間になってしまうでしょう。この娑婆世界で生きていくには、お釈迦様の時代の考え方を応用しながら、欲とうまくつき合っていく必要があるのです。
そこで覚えておきたいのが、欲のコントロールで指標となる「小欲知足」という考え方です。これは、「少ない欲で満足することを知る」という意味です。
欲がすべて悪者なのではありません。欲にも必要な欲と減らした方がいい欲があり、そのなかで心が満たされる状態に調整することが大切なのです。
たとえば、同じ欲でも「意欲」なら? 否定的にとらえる人はあまりいないでしょう。実際、意欲なしに経済は回らないし、やる気、元気がなければ、何事もなし得なくなってしまいます。
実は、お釈迦様も「無気力はいけません」と言っています。人は根源的には「生きたい」という欲をもっていて、私たちはその他のさまざまな欲と折り合いつけながら生きていく必要があるのです。
誰でも年をとれば体力の低下とともに欲望も自然と少なくなっていくので、放っておいても小欲知足の状態になっていくのかもしれません。
苦しみがなくならないこの世で、力強く根を張り、蓮華のように清らかな花を咲かせるために、まずは「自分が本当に欲しいものは何だろう?」といったところから考えて、小欲知足を実践してみましょう。