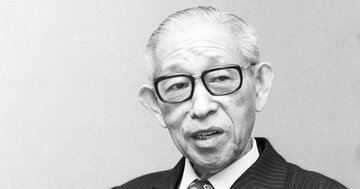効率的な情報獲得が
企業の競争力を決める
一方で、意思決定は限られた情報で果敢に行うもの、という意識が強すぎて、情報量が軽視されていることもあります。そのため、経営という高い次元の意思決定において、情報量が重要視されていないように感じることも意外と多くあります。
経営は複雑です。不確実性の高い未来に対する意思決定のため、変数が多く、情報の多さによって意思決定の精度が上がる実感を持てないことが多いからかもしれません。
しかし、必要以上に少ない情報で意思決定を迅速に下すことを過剰にとらえすぎて、情報収集がおろそかになることは避けるべきです。非常に複雑であるからこそ、情報が十分になることはありませんが、だからといって少ない情報で十分ということはありません。
情報プラットフォームの発達やウェブでの情報収集、人へのアクセスの容易さも相まって、情報獲得の投資対効果が以前よりも高くなり、小さな投資で圧倒的な情報量や精度を獲得できるようになっています。
情報獲得への向き合い方は変化しているというのが実際で、これまでのように限定情報で迅速な意思決定を行うというよりも、限られた時間のなかで、より効率的に情報獲得投資をしながら、意思決定の精度とスピードを両立させる努力を意識的に行えるようになりました。こうした情報獲得手段の多様化や進歩を踏まえ、この活用方法に習熟している企業とそうでない企業の差分は、さらに大きくなっていくかもしれません。
企業の競争力においても、意思決定の精度とスピードをいかに高めるか、そのための情報獲得基盤をいかにうまく活用していくかが、今後大きな分かれ目になっていくと思います。
意思決定に必要な
情報のとらえ方とは
情報をたくさん集めたとしても、いっこうに決断ができないという人もいます。
情報があればよい意思決定ができるかといえば、そうとは限りません。日ごろから一生懸命インプットに努めて情報を集めるのに長けていたり、高い処理能力があったり、膨大な情報を持っている人もいます。そうした人であれば最適な意思決定ができるわけではないのです。実際に皆さんの周りにもいるのではないでしょうか。
重要なのは、仮説や自分の意思を確認することです。自分の意思を確認するためにミッションを言語化してみる。そして、仮説を構築して、その視点で情報をとらえていく。そうすることで、情報が少なくてもよい意思決定ができるかもしれないですし、たくさん情報を集めることでの投資対効果が高くなるはずです。