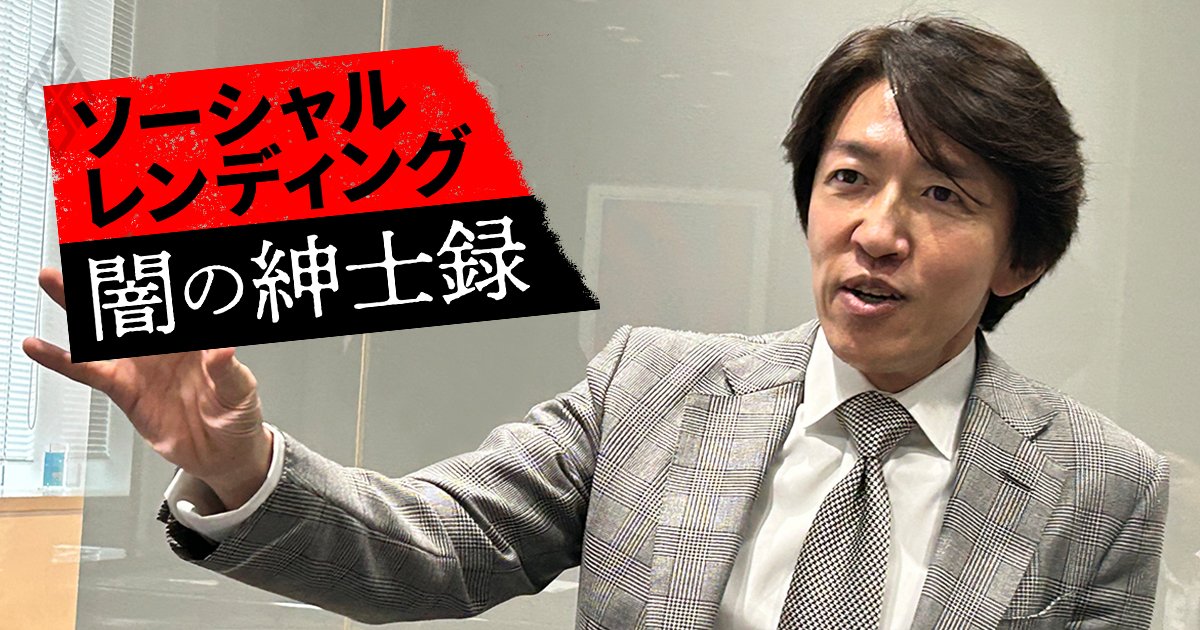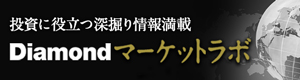「関税の帰着」はかなり複雑な問題
外国企業への「後転」は非現実的
しかし、「関税の負担者は誰か?」という問題は、実はかなり複雑な問題だ。これは、経済学で「税の帰着」(Tax incidence)として議論されている。
第1に、「通常はアメリカの輸入業者は関税を負担することはない」としたが、その一部を負担することはあり得る。ただし、輸入業者はアメリカの企業であって、日本の企業ではない。
第2に、日本のメーカーがアメリカへの輸出価格を変えないとすると、日本車は価格競争上、不利な立場に置かれることになる。その結果、売り上げが減少し、利益が減ることがあり得る。この場合には、日本のメーカーも関税引き上げの一部を負担する。
第3に、関税による価格競争力の低下を避けるため、日本メーカーは価格を下げるかもしれない。販売台数を関税賦課前と同じに保つためには、課税後の価格が2万ドルになる必要があるから、輸出価格を1.6万ドルにする必要がある。
そうすれば、売り上げが1台あたり0.4万ドル、つまり60万円だけ減る。それに伴って利益も減るだろう。また、コスト削減を部品メーカーなどに求めることもあり得る。こうした場合にも、日本のメーカーが一部を負担する。
第2、第3のケースでは、確かに日本の企業が関税の一部を負担することになる。これは経済理論で「関税の負担が生産者に後転される」といわれる現象だ。
後転がどの程度の大きさのものかは、さまざまな条件に依存する。仮に日本車が非常に強い競争力を持ち、価格が上がっても販売量があまり影響を受けないとすれば、後転効果は少ないだろう。
少なくとも「関税の負担がすべて外国企業に後転する」とする主張は、非現実的なものであり、経済分析では否定されている。
最大の問題は「経済厚生のロス」
生産性も低下、結局は米国に損失
関税がもたらす問題は、以上にとどまるものではない。もう一つの大きな問題として、「経済厚生の損失」(Deadweight Loss)がある。これは関税が課される結果、生産量が本来あるべき水準より少なくなってしまうことによってもたらされる問題だ。
まず、関税がなければ、性能の良い日本車がもっと利用され、アメリカ人の生活水準は向上する。ところが関税でその価格が引き上げられてしまうと、日本車の利用が減少する。それによって人々の生活は貧しくなる(これは経済学で「消費者余剰の減少」と呼ばれる)。
それだけではない。効率の悪いアメリカ車の生産に、従来よりも多くの資源が使用される結果、アメリカ経済全体の生産性が低下する(これによる損失は経済学で「生産者余剰の減少」と呼ばれる)。
こうした損失が、関税収入の増加というプラスの効果を打ち消してしまうかもしれない。
経済厚生の損失は「誰も得しない損失」だ。日本の得にも、アメリカの得にもならない。
こうした関税の生産者への後転の大きさや経済厚生の損失がどの程度のものになるかは、実証分析をしてみないと分からない。
トランプ関税の及ぼすこの問題について多くの調査や実証分析が行われているが、その結果は、関税率の引き上げは、アメリカにとって利益をもたらすのではなく、むしろ損失をもたらす場合の方が多いということになっている。
つまり、トランプ氏が主張するように、関税の賦課によってアメリカが豊かになることは期待できない。
(一橋大学名誉教授 野口悠紀雄)