そのためAさんの児童福祉司とのやりとりを見ればわかるように、愛情の認識が大きくずれてしまう。
結果的にはAさんに六法全書の条文を読ませ、自分のしている行為を客観的に捉えさせ、それが愛情ではないことを理解できたことは大きな意義があった。そのことが母親の行動改善に結びついたと言える。
そのように考えると、このような自閉スペクトラム症の特性を持つAさんに対して、「愛情をかけてあげてください」「娘さんの気持ちをもっとわかってあげてください」という言葉がけが果たしてよかったのだろうかと思ってしまう。
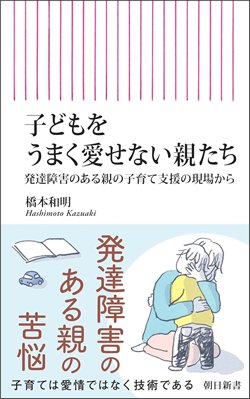 『子どもをうまく愛せない親たち 発達障害のある親の子育て支援の現場から』(朝日新聞出版、朝日新書)
『子どもをうまく愛せない親たち 発達障害のある親の子育て支援の現場から』(朝日新聞出版、朝日新書)橋本和明 著
愛情が何かわからず、他者への配慮がしにくい人にそれを強く求めることは相手をますます混乱させ、事態を悪化させてしまうことになりはしないだろうか、と考えさせられるのである。
筆者はこのAさんの事例に出会って、支援者が愛情を振りかざすような支援を親に要求したり、それを目指していこうとしたりすることにどこまで効果があり、そして意味があるのかと考えるようになった。
もちろん、愛情についての共通認識があり、それを理解し感じ取れる人であれば、こうしたアプローチも悪くはない。
しかし、問題は自閉スペクトラム症の特性があるなど、それがしにくい人である。彼らにとっては、抽象的でわかりにくい愛情をかけることが混乱を招き、逆にそのことが弊害になることがある。
それよりも、子育ての具体的な方法や、時には独自の養育の工夫を目の前の親と一緒になって考えていくことの方が、虐待防止には有効であると思えたのであった。







