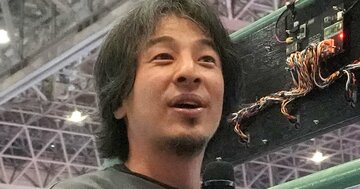いくつか例を挙げるなら、実際には4.9%であった当時の失業率を、42%であると述べたり、バラク・オバマ元大統領がイスラム過激派ISISの「創始者」であると述べたりした。また、大統領に就任したトランプは、その一年目において「欺瞞に満ちているか、または誤解を招く発言」を「計2140回(編集部注/『真実の終わり』ミチコ・カクタニ、岡崎玲子訳、集英社、2019年)」行ったという。
こうした発言の真偽は、少し調べれば、あるいは調べるまでもなく、嘘であると判明するものばかりだった。しかし、トランプは自分の発言が嘘ではないことを証明するための工作をほとんど何も行っていなかった。
彼は、自分の発言が嘘だと思われることに、まったく関心を寄せなかった。それは、たとえ嘘であったとしても、その発言が世論に対して政治的な影響力を持つということを、知っていたからである。この意味で彼の態度は、テシックの言うポスト・トゥルースの、一つの先鋭化であったに違いない。
客観的事実よりも
感情へのアピール
2016年、オックスフォード英語辞書は、「今年の言葉」として「ポスト・トゥルース」を選出した。そこでこの言葉は次のように定義されている。
(Oxford Languages, Word of the Year 2016)
もちろん、1992年と2016年とでは、まったく同じ状況に置かれているわけではない。その違いはいったいどこにあるのだろうか。
日本近代文学研究者の日比嘉高は、2016年を大きく特徴づける要素として、情報環の変化を挙げている。
インターネットが普及し、ソーシャルメディアが発達した現代において、人々はある種の情報過多のなかで生きている。政治・健康・環境・経済などの様々な分野に専門家がおり、その意見はしばしば対立することもある。
特にインターネット上では、専門家と素人の発言の境も曖昧になる。このような環境のなかで、人々は、そもそもどの情報を信じたらよいのかが分からなくなっていく。
情報過多の状況にあるからこそ、正しい情報を取捨選択する能力、いわゆるリテラシーが重要であると言われている。しかしそれは容易に身に付くものではないし、情報について判断するためには経済的・時間的コストもかかる。
このような環境において、人々は自分が信じたい情報を信じるようになってしまう。なぜなら、情報そのものを見ても、その正誤は判断できないため、そもそも正誤が情報を評価する基準ではなくなってしまうのだ。それに取って代わるのは、その情報を信じたいか信じたくないか、という情念なのである。