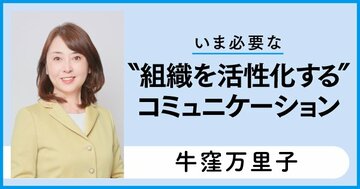“形だけの多様性”では、社会も組織も良くならない
ダイバーシティやインクルージョンの推進、多様な人材の活躍――こうした言葉が社会に浸透しつつある一方で、長谷川さんは「日本社会における多様性の理解には、なお大きな課題が残っている」と感じている。
長谷川 「女性を何人入れるか」「外国人を登用したい」など、表面的な対応にとどまり、単なる“数合わせ”で終わってしまっている場面を、私は何度も見てきました。ポーズとしての多様性は増えましたが、その意味を深く理解している人は、実のところ、それほど多くないと感じています。たとえば、会議や審議会で「女性委員を追加しましょう」という方針のもとに女性が加わっても、その女性が任されるのは本筋から離れた分野であることが少なくありません。総務、財務、人事といった意思決定の中枢ポジションは、いまだに男性が多数を占めています。本来、“多様性”とは、異なる意見や価値観を持つ人たちが集まり、それぞれの視点が交わることで議論が深まり、新たな価値を創造していくことに意味があります。しかし実際には、“ダイバーシティをやっています”という看板だけが先行し、中身がともなっていない状況が目立ちます。“形だけの多様性”では、社会も組織も良くなりません。
多様性という概念が広く知られるようになった一方で、現場では、その意義を実感できないまま、取り組みが形骸化しているケースも多い。「ポーズとして」ではなく、多様性の本質を組織に根づかせるには、何が必要なのか。
長谷川 人は「これは良くなるな」と実感しない限り、なかなか行動を変えようとはしません。理念や正論だけで現場を動かそうとしても、うまくいかないことが多いのです。「この人たちと一緒に取り組んだら、成果が出た」「考えが違う人がいたから、良い結果につながった」――そうした経験を積み重ねることで、「多様性は、やはり大切なのだ」と心から納得できるようになる。そう実感してはじめて、現場の考え方や働き方が少しずつ変わっていくのだと思います。