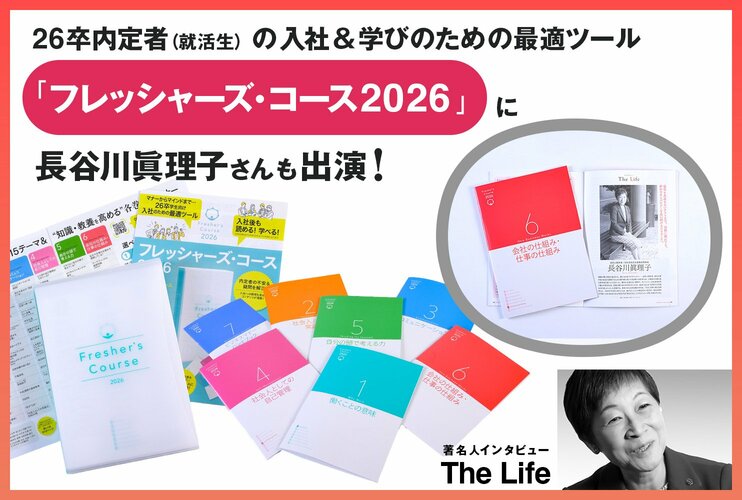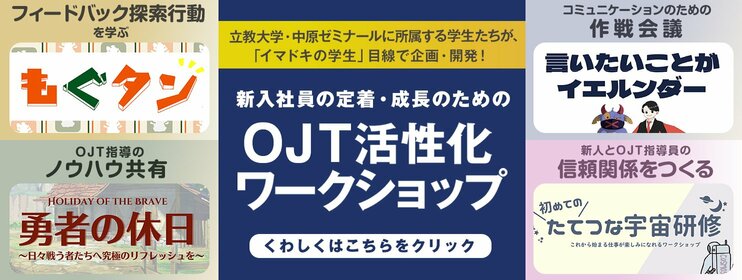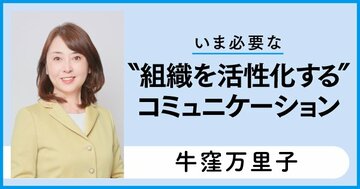失敗をおそれずにチャレンジできる場が新人を育てる
多くの職場では、新人の育成にあたって、「何を教えるか」に意識が向きがちだ。しかし、長谷川さんは「それ以上に、迎える側の姿勢が問われている」と語る。
長谷川 新人に対して、「この人はまだ社会のことを何も知らない」と最初から決めつけて、何から何まで教え込もうとする場面をよく見かけます。けれども大切なのは、「この人には、この人なりの経験や価値観、考え方がある」という前提で接することです。少しくらい失敗しても、「とりあえずやってみよう」と思えるような雰囲気があると、人はチャレンジできるし、成長していきます。最初からマニュアル的に細かく指示されると、「間違えてはいけない」という意識が強くなり、のびのびと動けなくなってしまうのです。
組織や職場にとって、新人が安心して試行錯誤できる環境づくりは欠かせない。若い世代が自分の意見を語ることに慎重になりがちな背景には、学生時代の経験が影響していると、長谷川さんは分析する。
長谷川 以前、大学のゼミで、学生たちが意見をまったく言わないことがありました。理由を聞いてみると、高校時代に「自分の考えは口にしないほうが安全」と考えるようになったというのです。内申書や評価を気にして、波風を立てないことが最善だ、と。そうした経験の積み重ねが、“議論をしない”“自分の考えを語らない”という習慣につながっているのでしょう。
議論を避ける空気は、職場にも蔓延しやすい。「対話がない場では、自分の信念も生まれない」と長谷川さんは言う。意見の違いをおそれずに語り合える場があることで、多様な考え方が刺激となり、思考を深めることができる。
長谷川 私は、昔から、“なぜそう思うのか?”を語り合うことを大切にしてきました。議論は、相手を打ち負かすものではなく、お互いの考えを深め合う場です。だからこそ、新人に対しても丁寧に耳を傾け、対話を通して信頼関係を築いていく――そのような土壌があってはじめて、“思い切って挑戦してみよう!”という気持ちが育つのだと思います。