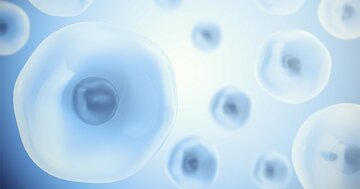付き合って半年ほど経ち、結婚の話が出始めた頃、小川さんはパートナーに、卵子凍結していることを話した。妊娠・出産を望むなら、急がないといけない年齢に来ていること。できることなら、子どもを産んでみたい“かもしれない”こと。後から後悔するのは嫌だなと思っていること。
話しているうちに、いろんな思いが去来して、自然と涙がこぼれた。その時、「あ、私って、やっぱり子どもがほしかったんだ」と思った。
「面と向かって彼と話しているうちに、“子どもがほしいかもしれない”と思っていた気持ちが、明確に“子どもがほしい”という気持ちに変わった。変わったというか、気づいたという感覚かも。“かもしれない”じゃなくなった。やっぱり“子どもがほしい”っていう気持ちって、相手がいることで、より明確になるんだって思った」
パートナーが示した
生殖医療への抵抗感
卵子凍結という医療技術そのものを知らなかったパートナーは、面食らった表情で、その話を聞いていた。
「彼は、前妻との間に子どもがいるし、これから新たに子どもを持とうとは考えていなかったみたいでした。でも何度か話し合いをして、私の思いを聞くうちに、“幸恵ちゃんがほしいなら、挑戦してみようか”って言ってくれました」
ただ、彼は凍結卵子を使うことには強い抵抗感を示した。この時、彼が生殖医療に対して抵抗感を持つタイプであることを、初めて知ったという。人の命は、自然な営みの中で授かるべきもの。不自然なことをすれば、どこかで無理が出てくるのではないか――それが彼の“抵抗感”の理由だった。
言い方はもっと優しかったが、端的に言えば、「自然に妊娠しなければ、そこで諦めるのはどうか」「医療の手を借りて“無理やり”妊娠するのはどうなのか」というのが、彼の意見だったという。